❕本ページはPRが含まれております
トランペット スースー音に悩むと、原因が自分の息づかいなのか、アンブシュアなのか、あるいは楽器の状態なのか判断しづらくなります。
本記事では、よくある要因と改善手順を整理し、今日から実践できる練習法に落とし込みます。演奏歴やレベルを問わず取り入れやすい方法を中心に、音がかすれる状況を減らし、狙った音色に近づけるための道筋を明確に示します。
基礎の見直しと継続的な観察を組み合わせれば、遠回りをせずに安定した発音へ近づけます。
この記事でわかること
- スースー音の主因を見分ける観点
- 息の方向とアンブシュアの整え方
- 効率的な呼吸と持続練習の進め方
- 整備点検と録音による改善サイクル
トランペット スースー音の原因を知る

息の漏れと唇の閉鎖不足を防ぐ方法
スースー音の多くは、唇の合わせ目や口角からの空気漏れに起因します。息が横へ逃げると空気圧が保てず、振動が不安定になって音が痩せます。
まずは鏡の前でロングトーンを行い、口角周辺の動きと頬の膨らみを観察します。頬が大きく膨らむ場合は、口角の支えが弱く息が散っている兆候です。
唇の合わせ目は過度に強く噛み合わさず、口角で支えるのが基本です。唇中央は柔らかさを保ち、口角から軽く内側へ寄せるイメージでセットします。息は歯列のわずかな隙間をまっすぐ前方へ送り、口輪筋の張りで横漏れを抑えます。
息漏れチェック
- マウスピースのみで中程度の息を送って音を出し、指先を口角の外側に近づけて風の漏れを感じるか確認します。
- マウスピースを付けた状態で同様に行い、楽器装着時の変化を比較します。
- 低音から中音のロングトーンで、息量を一定に保ったまま口角の支えを微調整します。息が直進すると音色が太く安定します。
口角を意識したアンブシュアの作り方
アンブシュアは、唇中央の柔らかい振動を口角の筋力で支える構造が基本です。笑顔のように横へ引きすぎると、合わせ目が薄くなり空気が抜けやすくなります。
口角は軽く内向きに締め、顎は下へ引きすぎず自然な位置に保ちます。歯の間は薄い名刺一枚が入る程度の隙間を目安にし、息の通り道を確保します。
基本セットアップの手順
- 口を軽く閉じ、唇の中心に意識を置きます。
- 口角をわずかに内側へ寄せ、頬を過度に張らないようにします。
- 息を前方へ細く速く送り、音の立ち上がりを揃えます。
- 音域を変えても口角の支えが崩れないか確認し、必要に応じてわずかに調整します。
以上の流れで、唇中央の振動を損なわずに空気圧を確保でき、スースー音の発生が減少します。
舌の位置を整えて息の流れを改善する
舌が低く平らだと息の通り道が広がりすぎ、スピードが不足して発音が曖昧になりがちです。中音域では舌先を下の歯の裏側付近に保ち、舌の中腹を軽く持ち上げることで息速を確保します。母音のイメージでは、eeに近い舌のアーチを作ると、狙った位置へ息が直進しやすくなります。
子音を使った発音練習
タやトゥなどの子音でアタックを整える練習は、息の向きと速度をそろえるのに役立ちます。タでは舌先を上歯茎付近から素早く離し、息が真っ直ぐマウスピースへ届く感覚を掴みます。
トゥでは唇の抵抗に対して息速を保つ意識が強まり、かすれを抑えられます。発音の後に息が途切れず流れ続けているかを確認すると、音の芯が太くなります。
腹式呼吸で息のコントロールを高める
胸や肩だけで吸う浅い呼吸では、息量や圧が不安定になり、音がかすれやすくなります。下腹部と背中側が同時に膨らむ腹式呼吸を使い、吸気と呼気の切り替えを滑らかにします。吸うときは喉を狭めず、息が静かに入る感覚を保つと、余計な力みが減ります。
ロングトーンと持続練習
メトロノームに合わせ、一定の拍数で吸い、一定の拍数で吐くサイクルを繰り返します。息の出口を細く保ち、音量と音色をキープすることを目標にします。呼気の最後まで音質が崩れないように管理できれば、実演時のフレーズでも安定を維持できます。
楽器の整備不良が音質に与える影響
楽器の状態が悪いと、演奏技術が整っていてもスースー音が発生しやすくなります。マウスピースの汚れ、ウォーターキーや接合部の微小な隙間、オイル切れやスライドの渋さは、息の流路を乱し振動効率を下げます。演奏前後の簡単な点検で、不要なロスを抑えられます。
| 不具合箇所 | 兆候 | 点検・対処 |
|---|---|---|
| マウスピース内の汚れ | 立ち上がりが鈍い、かすれが増える | ブラシで清掃し、乾燥後に装着 |
| バルブのオイル不足 | 抵抗が増え音が荒れる | 適量のバルブオイルを補充 |
| スライドの渋り | ピッチ調整で息が途切れる | スライド用グリスを塗布し可動確認 |
| ウォーターキーの不密閉 | 特定音域で風切りがする | パッドの当たりとネジを確認 |
| 接合部の緩み | 振動が伝わらず音が薄い | ネジ・管体の緩みを点検し修正 |
トランペット スースー音を改善する練習法

スースー音を改善する練習法
息の方向を確認するトレーニング
息の向きがわずかに外れるだけで、マウスピースの中心にエネルギーが乗らず、スースー音が増えます。片手をベル前方に置き、一定の距離で風の当たり方を感じ取るハンドテストを行います。
息が上下左右に散る感覚があれば、顎の角度と口角の支えを調整し、最も強くまっすぐ当たる位置を探ります。紙片をベル前に吊るして発音し、紙の揺れ方で息の直進性を観察する方法も有効です。
息が中央に集中すると紙の動きが一方向に安定します。低音域と中音域で同様に試し、音域が変わっても息の軸がぶれないか確認します。
リラックスして余分な力を抜くコツ
肩や首、顎に無意識の緊張があると、息の流れが途切れやすくなります。立奏時は両足を肩幅に、座奏時は坐骨でまっすぐ座り、胸郭の動きを妨げない姿勢を心がけます。息を吐きながら肩を落とし、喉の奥を広く保つ感覚をつくると、吸気も静かになります。
練習前の数分間は、ゆっくりとしたロングブレスで体の状態を整えます。アンブシュアをセットしたまま軽いハミングを行い、口周りの無駄な緊張を解いてから音出しに入ると、立ち上がりの雑音が減ります。以上の習慣化により、必要最小限の力で息が通り、音色が安定します。
専門家の指導で学ぶ正しい奏法
自己流での試行錯誤は大切ですが、客観的な視点が加わると改善が速くなります。指導者は、息の向きや舌の動き、口角の支えといった細部を観察し、課題に合った練習を提示します。
短時間のレッスンでも、最初の音出しから姿勢や呼吸の調整点を明確に示してもらえるため、練習の優先順位がはっきりします。
レッスンでは、長期目標と短期の到達点を共有し、録音やメモで変化を記録します。オンラインの活用も選択肢ですが、カメラ角度や音声環境を工夫して、息の方向や口元の動きが分かる映像を用意すると効果的です。
自分の音を録音して客観視する方法
録音は、主観と客観のギャップを埋める強力な手段です。スマートフォンでも十分で、マイクはベルから適度に離し、直線上を少し外した位置に置きます。和室や狭い部屋では響きが過多になりがちなので、複数の環境で試し、実音に近い条件を見つけます。
同じフレーズを、アンブシュアや舌の位置、息の速度など一要素だけを変えて録り比べ、波形や音量のばらつきも合わせて確認します。録音を聴き直す際は、立ち上がりのノイズ、音の芯、最後の消え際までの質感に注目すると、改善の方向性が具体化します。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
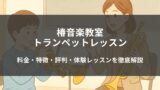
トランペット スースー音の克服まとめ
まとめ
- 口角を支点にして横漏れを防ぎ息を直進させる
- 舌の中腹をわずかに上げ息速を確保して発音を安定
- ロングトーンで音量と音色の均一さを日々点検する
- 顎と肩の緊張を解き自然な姿勢で呼吸を循環させる
- アンブシュアは中央を柔らかく口角で支える構造を維持
- 息の方向は手や紙片を使い可視化して微調整を続ける
- マウスピースと管体の清掃で不要な抵抗と雑音を削減
- オイルとグリスの管理で機構抵抗を抑え発音を軽くする
- 録音で主観のズレを把握し練習メニューを最適化する
- 子音の練習でアタックを整え息の流れを途切れさせない
- 吸気は静かに深く吐気は細く速く一定に保ち続ける
- 音域が変わっても口角の支えが崩れないか常に確認
- 目標音色を決めて練習記録を取り改善の軌跡を見える化
- 指導者の客観視点を取り入れ課題に合う練習へ集中
- 小さな改善を積み重ね継続習慣で再発リスクを下げる
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


