❕本ページはPRが含まれております
トランペット 高い音 コツを探している初心者に向けて、息の扱い方や唇のコントロール、舌の使い方、練習手順までを体系的に解説します。
音が当たらない、かすれてしまう、力んでしまうといったつまずきを、楽器の仕組みと基礎技術の両面からほどき、今日から取り入れられる具体的な練習メニューを提示します。遠回りを避けたい方が、無理のないフォームで音域を伸ばすための道筋を示します。
この記事でわかること
- 高音に必要な呼吸と息のスピードの作り方
- アンブシュアとマウスピースの当て方の要点
- かすれる原因の見分け方と改善手順
- 安全に音域を広げる練習の進め方
トランペット高い音のコツ 基本を理解する

基本を理解する
初心者が押さえるべき基礎練習
高音は偶然ではなく、基本動作の積み上げで届きます。最初に狙うのは、楽に出せる音を小さな音量で安定して伸ばすことです。音を伸ばす際は、息の流れを途切れさせず、音程と音色が揺れないかを耳で確認します。姿勢は骨盤を立て、胸を張り過ぎず、首や肩の余分な緊張をほどきます。
基礎のうちから、口角を横に引き過ぎないこと、顎を必要以上に前へ突き出さないことを習慣化すると、後々の高音で無理な力みを避けられます。これらの下地が、以降の呼吸・舌・唇のコントロールを支えます。
腹式呼吸で効率よく息を使う方法
腹式呼吸は大量の空気を静かに吸い、圧を保って細く速い息へ変換する準備になります。鼻・口いずれでも音が立たないよう静かに吸い、下腹部と背中側、肋骨の外側が均等に広がる感覚を持ちます。吐くときは胸や喉で押さず、下腹部から空気の柱を前方へ送り続けます。
息の圧は強くても、のどは開いたままが原則です。呼吸練習の段階で、秒数を決めて吸う・保つ・吐くを繰り返すと、演奏中の息切れや不安定な音色を防ぎやすくなります。
息の要素と練習の対応表
| 要素 | 狙い | 練習の例 |
|---|---|---|
| 吸気量 | 余裕の確保 | 4拍吸う→2拍保持→8拍吐く |
| 吐く速度 | 高音の振動支援 | 小音量のロングトーンで均一維持 |
| 体内圧 | 息の柱の安定 | 息を溜めてから細く前方へ放出 |
| のどの解放 | 不要な抵抗排除 | あくびの喉でスーッと吐く感覚 |
| 姿勢 | 気道の確保 | 壁立ちで頭・背中・骨盤を整える |
舌の位置を意識して息をスピード化
高音では息の速度が鍵となります。舌の前半を軽く持ち上げ、口腔内をやや狭くすることで、同じ息量でも流速を上げられます。発音はタ行系のアタックを基本に、強く叩かず短く触れる意識で発音します。舌を上げるほど明るい音色になりやすい一方、上げ過ぎは詰まりや疲労を招きます。
鏡で口角や顎に余計な動きが出ていないか、ロングトーンで確認しながら微調整すると、スムーズな切り替えが身につきます。
高い音 かすれるときの原因と対策
かすれは、息の速度不足、過剰な口圧、または唇の隙間が広すぎることが主な要因です。まず息の流れを途切れさせないことを最優先にし、息を速くしたうえで音量は控えめに保ちます。次にマウスピースの押し付けを弱め、唇の接点をわずかに近づける方向で調整します。
アタック直前で息を止める癖がある場合は、先に息を流し始めてから舌を離すと安定しやすくなります。これらを段階的に試すと、原因の切り分けが容易になります。
アンブシュアを安定させるポイント
アンブシュアは唇の端が支点となり、中央の振動域を自由に保つ形が基本です。上下の唇は均等に当てる目安から入り、上下比率は個人差に合わせて微調整します。
押し付けで音程を上げようとすると振動が止まりやすいため、唇の隙間を保ちつつ息の速度で支える意識に切り替えます。長音では口角と顎の静けさを保ち、鏡で不必要な歪みが出ていないかを確認すると、フォームが定着します。
楽に出せる音域から少しずつ広げる練習
音域拡張は、今楽に出せる基準音から半音または全音ずつ上げるのが安全です。小さな音量でロングトーン→短いスラー→短いスケールの順に負荷を増やします。
高音ばかり続けず、基準音に戻してフォームと息の感覚をリセットすることで疲労を抑えられます。練習の最後は必ず低音域でクールダウンを行い、翌日に響く硬直を避けます。
トランペットで効果的に学ぶ高い音のコツ

効果的に学ぶ高い音のコツ
適切なマウスピースの当て方を探る
当て方は唇の中心に軽く置き、口角で支えて中央は自由に振動させます。上下の割り合いはまず均等を出発点にし、音色や反応で最適値を探します。
角度は楽器の向きと顔の形状で微妙に変わるため、鏡と録音で反応の良い位置を見つけます。押し付けは必要最低限に留め、音が詰まる前に息の速度と舌の位置で調整する流れを身につけると、負担を増やさずに高音へアプローチできます。
息を溜めてから放出する呼吸の工夫
高音前は吸ってすぐ吐くより、体内で一拍保持してから放出すると息の柱が整います。保持中は喉を締めず、下腹部で静かに圧を感じる程度にとどめます。
放出は細く速く、音量は欲張らず、音程とアタックの安定を優先します。息の切り替えが荒くならないよう、メトロノームに合わせて吸う・保つ・吐くを定型化すると、実演でも安定が再現しやすくなります。
低音域の安定が高音への基礎となる理由
低音が整うと、唇の接点や舌の動き、息の速度を可視化しやすくなります。低音域で均質な音色と確かなピッチを作れる奏者は、同じ原理を高音へスライドできます。
低音でのロングトーン、低→中へのスラー、同音反復のアタック練習を丁寧に行うと、上の音でも過剰な力に頼らずに済みます。以上の点を踏まえると、高音の成功率は基礎域の完成度に比例すると言えます。
音を小さく長く伸ばす練習の重要性
小音量のロングトーンは、息の速度・唇の隙間・舌の位置を精密にそろえる訓練になります。音の立ち上がりを滑らかにし、音色のザラつきやビブラートの暴れを抑える効果もあります。
時間を区切って、一定の音量・音程・音色を維持する課題を与えると、集中すべき感覚が明確になります。要するに、静かな長音の精度が上がるほど、高音でのコントロールが自然に向上します。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
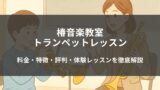
トランペット 高い音のコツまとめ
まとめ
・息は大量ではなく速さを優先し喉を開いたまま保つ
・舌をわずかに上げ口腔を狭め流速を高めて支える
・マウスピースは押さえず口角で支え中央を自由に保つ
・アンブシュアは静かに固定し唇の接点を適度に近づける
・高い音 かすれる症状は息速不足と過圧をまず疑う
・吸って一拍保持し細く前方へ放出する流れを作る
・低音域の均質な音色と確かなピッチを日々整える
・小音量ロングトーンで音の揺れと雑味を点検する
・楽に出せる基準音から半音ずつ安全に広げていく
・高音練習は短時間で区切り基準音でフォームを戻す
・姿勢は気道を確保し肩と顎の無駄な緊張を避ける
・アタックは短く軽く舌で触れ息の流れを止めない
・鏡と録音で口角や顎の余計な動きを常に確認する
・練習の締めに低音でクールダウンして疲労を残さない
・日々の記録で最適な当て方と比率をデータ化して更新する
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


