❕本ページはPRが含まれております
トランペット 音が出ない 初心者という悩みは、息の通し方や唇の使い方のコツがつかめていないだけのことが少なくありません。
この記事では、音が出る仕組みを理解しながら、道具がなくても取り組めるながら練習やバズィング、口周りの筋肉の使い方、マウスピースから楽器本体へと進む段階的な手順を整理して解説します。正しい手順を知ることで、無駄な力みを避け、短時間でも効果を積み上げられるようになります。
この記事でわかること
- 音が出る仕組みと基本の動作を理解できる
- 家でもできるながら練習の方法がわかる
- バズィングから楽器本体までの手順が明確になる
- つまずきやすい原因と対処の要点を把握できる
トランペットの音が出ない初心者の原因

音が出ない初心者の原因
音が出る仕組みとバズィング
トランペットは唇の振動が管内の空気を震わせることで音になります。鍵となるのは、唇を軽くすぼめて息を通し、安定した振動を作るバズィングです。
最初は小さな息から始め、唇の中央で空気が細く速く流れる感覚をつかみます。音量よりも、連続して同じ高さの振動が続くことを優先しましょう。
息を一気に押し出すと唇が開きすぎて不安定になります。逆に弱すぎると振動が生まれません。浅い息から始めて、少しずつ流量を上げながら、唇の合わせ目が跳ね返る感触を探ると、無理なく音の芯に近づけます。
よくあるつまずき
息を止めてから強く吹こうとすると、開始時に唇が固まり音が割れやすくなります。息を止めずに、吐きながら唇を合わせていく順序を意識すると、立ち上がりが安定します。
鏡で確認するおちょぼ口
おちょぼ口は、唇の端を引きすぎず、中央に軽く厚みを持たせた形です。鏡を使うと、上唇がわずかに前へ出て下唇をやさしく被う配置を客観的に確認できます。上下の歯は軽く離し、顎を固めないことがポイントです。
視覚フィードバックは学習を加速します。毎日数十秒でも鏡の前で形を作り、眉間や肩に余計な力が入っていないかを観察します。唇の中央が薄すぎると息が広がってしまうため、中央に細い通り道を作るつもりで形を整えます。
息の量と唇の開きのチェック
音が出ない多くのケースは、息の量と唇の開きのバランスが合っていません。息が多すぎると唇が押し広げられ、少なすぎると振動が起きません。自分の傾向を把握し、微調整を重ねることで最短距離で改善できます。
下の表は、ありがちな状態と対処の目安を整理したものです。
| よくある状態 | 原因の目安 | 調整のヒント |
|---|---|---|
| 息を入れても空気音だけ | 息が多すぎて唇が開く | 一度息量を半分にし形を先に作る |
| 低いブーが一瞬で消える | 息が弱く速度が遅い | 小さく鋭い息へ切り替え持続を意識 |
| 音が割れて高く跳ねる | 顎と喉の力み | 口の中をあくび形にして脱力 |
| 口角が横に広がる | 口輪筋が弱い | おちょぼ口で中央に厚みを作る |
音は結果であり、操作は原因です。どの操作を変えたら結果がどう動くかを一つずつ検証する姿勢が、最短の上達に直結します。
顔と口輪筋の基礎トレ
口輪筋や頬の筋肉が働くと、唇の中央に適切な厚みを保ったまま息路を細くできます。鏡の前で普通の顔からおちょぼ口を作り、また戻す動作をゆっくり反復すると、必要な筋活動を学習できます。数回で疲れる程度の軽い負荷で十分で、毎日の継続が効きます。
表情筋の役割を理解することも大切です。頬を内側に軽く寄せると息路が整い、口角を横へ強く引くと息が拡散します。望ましいのは、横に引くのではなく、中央へまとめる方向の力です。短時間でも、狙った筋肉だけを使う感覚を意識できると、音の立ち上がりが滑らかになります。
力みを抜くための姿勢
姿勢は呼気の安定に直結します。立位では土踏まずの上に重心を置き、膝をロックせず、骨盤から背骨を上へ伸ばします。座位では坐骨で体を支え、背もたれに寄りかかりすぎないようにします。胸を張るのではなく、胸郭が自然に上下へ広がる余地を確保するイメージが有効です。
喉の奥を詰める力みは音を不安定にします。口内をやや広く保ち、舌先は下の歯の裏に軽く触れる程度にして、息の流れを邪魔しないようにします。以上の点を踏まえると、無理のない姿勢が息の速度と方向を整え、結果としてバズィングの安定につながります。
トランペットの音が出ない初心者の解決策

音が出ない初心者の解決策
ながら練習で毎日続ける
ながら練習は、音を出さずに実施できるため、生活の合間に積み重ねやすい方法です。通勤やテレビ視聴の合間などに、おちょぼ口の形作りやフェイスセットの保持を数十秒行うだけでも、翌日の感触が変わります。
短い頻度の反復は、長時間の一気練習より学習効率が高いことが多く、初心者に適しています。形だけではなく呼吸も合わせると効果が増します。
鼻から静かに吸い、唇の中央を保ったまま細く長く息を吐く練習を重ねると、実際に音を出す段階で過剰な力が抜け、立ち上がりのブレが減ります。要するに、道具を使わずに基礎の手応えを高めるのが、ながら練習の狙いです。
バズィングの手順とコツ
手順は単純です。おちょぼ口を作り、上唇で下唇を軽く被い、息を少量から通して下唇をゆっくり戻し、唇の振動を捉えます。開始直後は小さな音で構いません。同じ高さで1〜2秒保てるようになったら、少しずつ時間を伸ばしていきます。
安定させるコツ
息の入口と出口を意識して、腹部からの圧を一定に保ちます。顎に力が入ると振動点がずれるため、あくびの喉で息の通り道を確保します。息を強くするより速くするイメージが、狙った高さを保つ助けになります。
チェック表
| 観点 | 良いサイン | 見直すポイント |
|---|---|---|
| 立ち上がり | ふっと自然に鳴り始める | 息をためずに吐きながら形を作る |
| 持続 | 同じ高さで2秒以上保てる | 息量より息速を優先する |
| 音色 | 空気音が少なく芯がある | 唇中央の厚みを保つ |
これらのことから、手順を分解して一つずつ整えるほど、短期間での安定に近づけます。
マウスピースで音を試す
バズィングで感覚を得たら、マウスピース単体での発音に進みます。口元の形はそのままに、リムで唇の中央を軽く支え、息の角度をわずかに下方へ向けると音が集まりやすくなります。最初は音程を気にしすぎず、短いトーンを均一に並べることを目標にします。
マウスピースは増幅器ではなく、振動を受け取り方向づける器具です。息を増やして鳴らすのではなく、バズィングで得た振動の質を保つ意識が大切です。安定して複数回発音できるようになれば、楽器本体でも立ち上がりが格段に楽になります。
楽器本体へ移行する流れ
マウスピースでの発音が続けて成立したら、本体に装着して低い音から試します。最初は短い音で、姿勢と息の方向を確認しながら、音の芯と響きの違いを感じ取ります。楽器が重くなる分、腕や肩に力が入りがちなので、保持の間も呼吸の自由度を失わないことが鍵となります。
段階的に取り組むと無理がありません。低音域での安定が得られたら、中音域へ広げ、最後に音量のコントロールへ進みます。以上の流れにより、負荷を上げても基礎が崩れず、長く吹いても疲れにくいフォームが身につきます。
ストロー割りばしつまようじ練習
細くて軽い棒状のアイテムを、歯や舌を使わず唇の力だけでくわえ、水平に保つ練習は、口輪筋のフォーカスを高めます。ストローから始め、慣れたら割りばし、さらに細いものへと段階を上げると負荷調整がしやすく、狙った筋肉の持久力が育ちます。
この練習では、唇の中央を締めすぎずに厚みを維持する感覚を得やすい利点があります。水平を保てない場合は、口角で引っ張る癖が原因になっていることが多く、中央へ寄せる方向へ意識を変えるだけで持続時間が伸びることがあります。
安全に行うための注意点
練習時の安全配慮は欠かせません。自治体の安全啓発資料では、口に物をくわえる行為は誤飲や転倒時のけがのリスクになるとされています。
尖った道具の取り扱いについても、取扱説明の一般的な注意事項では、周囲に人がいない静かな場所で実施し、走行中や歩行中には行わないとされています。
これらの情報がありますので、細い道具を使う練習は必ず静止した安全な環境で行い、未就学児の手の届かない場所で保管する配慮が求められます。
騒音面のトラブル回避も大切です。集合住宅の案内では、鳴音を伴う練習は時間帯や場所の配慮が必要とされています。無音でできるながら練習やバズィング中心で基礎を整え、実音の練習は防音の工夫をした時間帯に限定すると、周囲と自分の集中双方を守れます。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
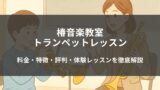
初心者がトランペットの音が出ない時の対策まとめ
まとめ
- 音は唇の振動と息の速度の両輪で生まれる理解を持つ
- 鏡でおちょぼ口を確認し中央の厚みを保つ感覚を養う
- 息量より息速を優先し小さく鋭い流れを作る
- 立ち上がりは息を止めず吐きながら形を整える
- 口輪筋と頬を中央へ寄せる方向で働かせる
- 姿勢は胸を張らず呼吸が自由になる位置を探る
- ながら練習で短時間の反復を毎日に組み込む
- バズィングは同じ高さでの持続を第一目標にする
- マウスピースでは振動の質を本体に渡す意識を持つ
- 本体移行は低音から中音へ段階的に範囲を広げる
- ストロー割りばしつまようじで中央維持を鍛える
- 安全配慮として静止した環境で誤飲を避けて行う
- 騒音配慮で無音の基礎と実音の時間帯を分ける
- つまずきは表で原因と対処を一つずつ検証する
- トランペット 音が出ない 初心者の悩みは手順で解ける
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


