❕本ページはPRが含まれております
トランペットの音がかすれる悩みは、息を十分吸っているのに鳴らせない、高音で細く不安定になるなど、練習の質や本番の結果に直結します。
この記事では、原因の見極めから改善の手順までを体系的に整理し、息のコントロールと舌の使い方、アンブシュアの再点検、体全体の使い方までを実践的に解説します。検索意図に合う具体策を示し、演奏の再現性と安心感を高める道筋を提示します。
この記事でわかること
- かすれの主因と見分け方が分かる
- 息と舌の連動による改善手順が分かる
- アンブシュア再構築の考え方が分かる
- 本番で安定させる練習設計が分かる
トランペット 音がかすれる原因と考え方

息のコントロール不足が与える影響
十分に吸っても息が胸や肩、喉でせき止められると、マウスピースへ届く空気の流量と圧力が不足し、音がかすれやすくなります。
吸気量よりも、楽器に流れ込む呼気の質と安定が演奏を左右します。特にフレーズの入りや長休符明けは、息の解放が遅れると初速が弱まり、アタックが不鮮明になります。
息の通り道を塞ぐ要因は、肩の不要な力み、胸郭の固定、喉の狭まりに集約されます。これらは無意識に起きやすいため、呼気開始のタイミングで体を解放する意識が鍵となります。息が楽器にまっすぐ流れる状態を作ることが、かすれの予防につながります。
舌の位置と空気の流れの関係
舌は気流のバルブのように働きます。舌先が上がり過ぎる、根元が落ち過ぎる、あるいはアタック直前に舌で息を止めると、気流の連続性が損なわれます。
理想は、音域に応じて舌面の高さを滑らかに変え、気流を細く速くしたい時は舌面をやや高め、広くゆったり流したい時は低めに保つことです。
音価が短い場面でも、舌で完全に息を遮断するのではなく、気流を流し続けた上で舌先の接触だけを最小限にします。こうした微調整が、アタックの明瞭さとかすれの抑制に直結します。
腹式呼吸だけでは不十分な理由
腹式呼吸は有効ですが、それだけでは音の芯や投射が不足しがちです。演奏では、吸った空気を体内で適切に加圧し、口元へ安定供給する工程が必要になります。腹筋強化だけに偏ると、上体や喉が固まり、かえって息の出口が狭くなります。
体内圧と流量のバランス
- 体幹で圧を作る一方、喉と口腔は解放する
- 目標音量に対し、圧と流量を同時に最適化する
- アタック直前に圧を先行させ、舌で過度に止めない
よくある勘違いと修正の目安(比較表)
| 観点 | よくある勘違い | 有効な考え方 |
|---|---|---|
| 呼吸 | 大きく吸えば鳴る | 吐き始めの安定が音を決める |
| 力の入れ方 | 腹筋を固めて押し出す | 体幹で圧を作り喉口腔は柔らかく |
| アタック | 舌で完全に止めてから出す | 気流は流し舌は最小の接触に留める |
高音が出ないときの共通パターン
高音でかすれる場合、多くは息の速度不足、舌面の高さ不適合、アンブシュアの締め過ぎの三つが重なります。唇だけを強く寄せると振動が拘束され、気流の通り道が消えます。息の速度を上げるには、体幹の圧を高めつつ口腔の通路を整えることが有効です。
また、長休符明けの高音は心理的緊張で肩や喉が固まりやすく、初速不足を招きます。直前に浅いブレスと軽いノンタンギングで気流の通り道を思い出してから本番の音に入ると、成功率が上がります。
アンブシュアの崩れを見直す視点
アンブシュアは唇だけではなく、顎、頬、口角、舌、歯並び、マウスピースの当て方を含むシステムです。崩れの兆候は、口角の過緊張、上下の圧力差、マウスピースの位置の過度な上下、長時間での持久低下などに現れます。
再構築では、音域別に必要な唇の自由度を確保し、気流に対して唇が自発的に振動する環境を優先します。小音量から倍音列を丁寧にたどり、振動の質を確かめながら安定域を広げていくと、かすれが減り、音色の芯が戻ります。
トランペットの音がかすれる改善方法と練習

改善方法と練習
空気圧を高めるための基本練習
体内圧を安全に高める練習は、喉や肩を固めずに体幹で圧を作る感覚を養います。ストローや狭い抵抗器具を用いた呼気トレーニングは、息の速度と持続を自覚しやすく、マウスピースに接続したロングトーンへ移行すると効果が定着します。
手順の一例
- 楽な姿勢で鼻から深く吸い、下腹と背中の広がりを感じる
- 口腔を縦に保ったまま、細く長く息を流す
- 吐き始めの0.5秒で圧を作り、以後は一定流量を維持する
- マウスピースでのブズィングに置き換え、同じ圧と流量を再現する
- 楽器のロングトーンに移行し、入口から出口まで変化がないか確認する
圧が高まるほど喉が狭まりやすいため、舌根や喉頭のリラックスを常にモニターします。短時間を高頻度で行い、疲労の蓄積を避けると質が維持できます。
舌と息を連動させるアプローチ
舌の形は音程と音色に直結します。母音イメージを活用すると、舌面の高さを視覚化しやすくなります。高音ではイーに近い舌面、低音ではオーに近い舌面を目安にし、気流を止めないまま舌先の接触でアタックを明確にします。
連動ドリル
- 気流を流し続け、タタタではなくダダダの発音感で連続発音
- メトロノームに合わせ、同一気流上で舌だけを切り替える
- 音域を跨ぐときは舌面を滑らかに移行し、段差を作らない
この連動が作れると、強弱や音域の変化でもかすれにくくなり、アーティキュレーションの幅が広がります。
音のかすれを防ぐアンブシュア矯正
矯正は、口角で締めて唇中央を自由に保つ原則を土台に、マウスピースの当て方と圧の方向を整えます。唇を押し潰すと振動面が失われるため、圧は内向きではなく前方への気流に同調させます。
鏡で口角と顎の位置を確認し、低音から中音へは唇の厚みを保ちつつ気流を速め、高音では過度に口角を引き過ぎないよう注意します。短いロングトーン、スラー、柔らかなアタックの順に積み上げると、振動の質が安定します。
演奏時に体全体を使う意識
姿勢は気流の直線性を決めます。骨盤を立て、胸郭を前後左右に解放し、首から上は吊られている感覚を保つと、喉の通り道が確保されます。足裏の接地を安定させることで、体幹の圧が呼気へ素直に伝わります。
長時間の練習では、短い休憩を挟んで肩と胸のストレッチを行い、固まりを未然に防ぎます。体の使い方が整うほど、息や舌の改善効果が音に反映されやすくなります。
指導者に習うことで得られる効果
自己流では気づきにくい癖を客観視でき、練習の優先順位が明確になります。特に息の解放タイミングや舌の微細な動きは自覚しにくく、第三者の視点が上達を加速させます。
到達したい音色や音量に対して、日々の課題を具体化できるため、練習時間の密度が上がります。映像記録を活用し、姿勢やアンブシュアの変化を時系列で確認すると、再現性の高いフォームが定着します。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
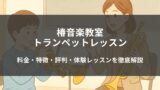
トランペットの音がかすれる対策まとめ
まとめ
- かすれは息の解放不足と通路の狭まりが主因
- 舌は気流のバルブであり完全停止は避ける
- 腹式だけに依存せず体幹で圧を準備する
- アタック前に圧を先行し気流を止めない
- 高音は息の速度と舌面高さの調整が要点
- 口角で支え唇中央の自由度を確保する
- マウスピース圧は前方の気流と同調させる
- ロングトーンからスラーへ段階的に積む
- 姿勢と接地で喉口腔の解放を保ち続ける
- 短時間高頻度で質を落とさず練習する
- 休符明けは浅いブレスで通路を思い出す
- 映像記録でフォームの再現性を高める
- 自己流の盲点は客観視で素早く修正する
- 練習設計は圧と流量の両立を常に確認する
- トランペットの音がかすれる根本を順に解く
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


