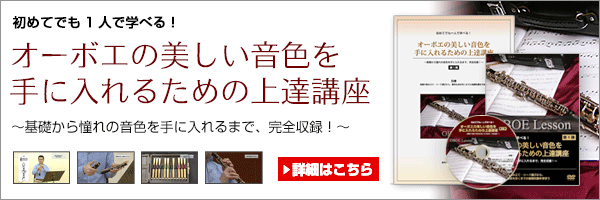❕本ページはPRが含まれております
オーボエ リード くわえ方を調べていると、何が正解なのか迷いやすいものです。口の形や息の使い方は体格や歯並びの影響を受けるため、教本どおりに試しても思うように鳴らないことがあります。
本記事では、汎用性の高い原則と再現しやすい手順に整理し、音の立ち上がりや持久力の改善につながる実践的なポイントを体系的にまとめます。基礎を押さえたうえで、負担を減らしつつ確実に反応する吹き方を身につけていきましょう。
この記事でわかること
- くわえ方の基礎設計とアンブシュアの狙い
- 息の量とスピードの考え分けと具体策
- 噛み過ぎを避けるチェックと修正手順
- 音程が下がる場面のリード調整の考え方
オーボエ リードのくわえ方の基本

リードのくわえ方の基本
アンブシュアの役割と目的
アンブシュアは、リードの振動を効率よく引き出し、息のエネルギーを音に変換するための口元の設計図です。個々に異なる歯や顎、唇の厚みの影響を受けるため、唯一の正解ではなく、共通原則を踏まえた最適化が求められます。
狙いは主に三つあります。第一に、少ない息の量でも反応する音の立ち上がりを確保すること。第二に、長時間の演奏でも口が早く疲れないこと。第三に、音程や音色を無理なくコントロールできることです。
そのためには、上下からの圧だけでリードを押しつぶすのではなく、横方向からの支えを作り、口腔内を狭めて息のスピードを上げるという二つの仕組みを組み合わせます。これにより、リード先端の振動を阻害せず、少ない力で安定した発音につながります。
口の中を狭くして息を加速
発音に必要なのは息の量を増やすより、息のスピードを高めることです。口腔内の通り道を適度に絞ると、同じ量の息でも流速が上がり、リードが素早く反応します。
実践では、舌の位置をやや高めに保ち、奥舌で喉側を広げすぎない意識が役立ちます。声に例えるなら、母音のウをイメージすると過度に開かず、狙った絞りを再現しやすくなります。
注意したいのは、先端を噛んで物理的に閉じるのではなく、口の中の形でスピードを作る点です。先端を押しつぶすと息の入口が狭まりすぎて流れが止まり、逆に反応が鈍くなります。口腔形状で加速、先端は開放、この分担が要になります。
唇をしっかり巻いて支える
唇はリードを包むクッションの役割を担います。下唇にリードを置き、下唇と一緒に内側へ巻き込み、上唇を添えて支えます。
巻き込みが浅いと、演奏中に唇が外へ滑り出し、支点が不安定になって音が揺れたり、疲労が早まったりします。反対に、巻き込みすぎて硬直すると、細かなニュアンスが出しづらくなるため、柔らかさと密着感の両立を目指します。
上唇は前歯の大きさや位置の影響を受けやすく、完全に巻けない場合があります。その場合でも演奏は成立します。上唇は添えて密着度を高め、主な支えは下唇と横方向の寄せに担わせると、無理のないセッティングになります。
横方向の力でウの口を作る
上下だけで挟むと、いわゆる噛みの状態になり、リードがつぶれて息が通らず、歯形が残るほどの負荷が生じやすくなります。これを避けるため、左右の口角から中心へ寄せる力を活用し、母音のウに近い形を作ります。
おちょぼ口を作ってから唇を巻き、巻いたまま再度おちょぼ口の形をつくると、横方向の支えが体感しやすくなります。
このとき、唇が前に飛び出すほどすぼめると、巻きの密着が崩れてしまいます。上下の密着は唇の巻きで確保し、左右の支えで先端をつぶさず固定する、という役割分担を意識すると、持久力と反応のバランスが整います。
リードは浅くくわえる理由
リードは先端部のみが主に振動します。先端が唇の内側に深く入りすぎると、息が振動点に効率よく届かず、発音が遅れたり、破裂音のように不安定になったりします。目安として、先端が下唇の中央付近に乗る位置で浅めにくわえると、少ない力で反応が引き出しやすくなります。
浅くすると従来のリードでは音程が下がる場合があります。その際は無理に噛まず、リード選択やセッティングで補正します。下表は深いくわえ方と浅いくわえ方の特徴の比較です。
| 観点 | 深いくわえ方 | 浅いくわえ方 |
|---|---|---|
| 反応 | 先端が働きにくく立ち上がり鈍い | 先端が振動しやすく発音が速い |
| 息の通り | 抵抗が増して息が詰まりやすい | 流れやすくコントロールしやすい |
| 音程傾向 | 無理に押すと上ずりやすい | 下がる傾向が出る場合がある |
| 口の疲労 | 噛みが増え疲れやすい | 横の支えで負担が分散しやすい |
オーボエ リードのくわえ方の実践
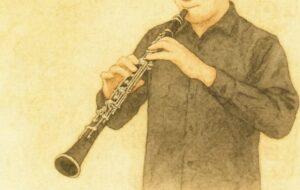
リードのくわえ方の実践
噛み過ぎを防ぐチェック項目
噛み過ぎは反応低下と疲労増大の主要因になります。演奏後にリード先端に明確な歯形が残る、音量を上げると急に詰まる、短時間でも口が保たない、といった兆候が見られたら見直しのサインです。確認の手順は次の通りです。
まず、リードをくわえた状態で軽く息を通さずに保持し、上下というより左右へ寄せて安定させる意識があるかを確かめます。
次に、母音をイからウへ静かに移行し、先端が押しつぶされずに振動の余地が残っているかを感じ取ります。仕上げに小音量のテストトーンを出し、息が細くても立ち上がるかを確認します。
これらの過程で詰まりを感じたら、先端の圧を抜き、口角から中央に寄せる支えへ比重を移します。短時間の基礎練の中に毎回このチェックを挟むと、噛み癖の再発を抑えられます。
息の量よりスピードを意識
長く吹くほど、量で押し切ろうとする傾向が出がちです。しかし、量を増やすほど疲労は加速します。狙うべきは少ない量で速い流れです。
口腔を狭めることで流速が上がり、リードが軽く反応します。練習では、同じ音量を保ちながら口腔の形だけを変えて、最小の息で最も早く立ち上がるポイントを探る方法が有効です。
支えは腹部や背筋の安定で作りますが、ここでも押し込みすぎないことが肝心です。空気圧を一定に保ちながら、口の形で微調整する発想に切り替えると、スタミナと表現の両立がしやすくなります。
下唇の中央に先端を置く
くわえる位置の基準は、先端が下唇の中央付近に乗ることです。ここを外すと、先端の振動点から息が外れ、反応や音色が不安定になります。鏡で横から確認し、巻いた下唇の中央に先端が来ているかを可視化すると、自己判断のズレを防げます。
もしこの位置だとリードが口内に入らない、または演奏中に先端が引っ込みすぎると感じる場合、唇の巻きが浅いか、くわえ込みが深すぎる可能性があります。巻きを丁寧に作ってから浅めに取り直すと、先端の振動を活かしたレスポンスが得られます。
前歯の大きさと上唇の巻き
上の前歯が大きい、あるいは前に出ている場合、上唇を完全に巻き込む形は取りづらいことがあります。この条件は演奏に致命的な障害ではありません。上唇は強く巻こうとせず、下唇と横方向の支えで主要な密着を確保し、上唇は密着の補助に徹すると安定します。
調整の手順として、下唇でリードを受け、下唇と一緒に巻いて密着を作ります。次に上唇を軽く添え、空気漏れを抑える程度に収めます。前歯に無理な圧がかからないため、持久力の面でも有利に働きます。結果として、先端の自由度が保たれ、繊細なダイナミクスが扱いやすくなります。
音程が下がる時のリード調整
浅めのくわえ方に切り替えると、使用中のリードでは音程が下がるケースがあります。この場合、噛みで補正しようとすると反応が損なわれます。推奨されるのは、リードの仕様を変えて口元の設計に合わせることです。短めのリードや、やや細めの仕様に切り替えると、浅いセッティングでも音程の芯が戻りやすくなります。
調整の考え方を簡単に整理します。
| 症状 | 考えられる要因 | アプローチ |
|---|---|---|
| 浅くすると音程が下がる | 現在のリードが長め・重め | 短めや細めの個体を選ぶ |
| 反応は良いが音が軽い | 先端が働き過ぎ | 唇の密着を見直し息を安定 |
| 立ち上がりが遅い | 口腔が広い・深く噛む | 口腔を絞り浅めに取り直す |
以上の点を踏まえると、リードに口を合わせるのではなく、確立したアンブシュアにリードを合わせる発想が、演奏全体の安定に直結します。
オーボエにおすすめの音楽教室
オーボエをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のオーボエレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のオーボエレッスンを詳しく見る

オーボエ リードのくわえ方まとめ
まとめ
- 目的は少ない息で素早く反応させ持久力も確保する
- 口腔を狭めて流速を上げ先端の振動を引き出す
- 先端は噛まず口内の形でスピードを生み出す
- 唇は巻いて密着させクッションとして機能させる
- 上下の圧より横方向の寄せで固定を安定させる
- くわえる位置は先端を下唇中央付近に置く
- 浅めのセッティングで発音の俊敏さを得る
- 浅くして音程が下がる場合はリードを見直す
- 上唇は添えて密着補助し無理な巻きを避ける
- 息は量でなくスピード重視で疲労を抑える
- 噛み過ぎの兆候を日々チェックし修正する
- 口角から中央へ寄せる意識で噛み癖を防ぐ
- 鏡の確認で先端位置と口の形を可視化する
- リードは口に合わせて選び直しをためらわない
- オーボエ リード くわえ方は原則を軸に最適化する
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ