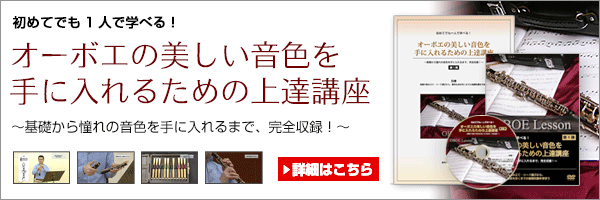❕本ページはPRが含まれております
オーボエ リード クローについて調べている方が、用語や判断基準が曖昧なまま練習を重ねると、音程の不安定や息の無駄遣いにつながります。
本記事では、オーボエ リード クローの仕組みと音色や倍音との関係、鳴らし方のコツ、状態別の見極め方、演奏に直結する調整の考え方を丁寧に整理します。基礎から実践までを一貫して解説し、明日からの選定やリード作りに迷いが残らないように導きます。
この記事でわかること
- クローの鳴らし方とチェック観点を理解できる
- 倍音との関係から音色と音程の傾向を掴める
- 状態別の原因と対処の方向性が分かる
- リード調整の優先順位と実践手順を学べる
オーボエのリード クローの基礎知識

クローの鳴らし方の基本
クローは、楽器本体に装着する前のリード単体で発生させるチェック音です。通常のアンブシュアよりも深く、削っていない硬い部分までリードをくわえ、安定した息で吹き込みます。
このとき下唇にかかる圧は過度に強くせず、上下均等に支えます。息の方向はまっすぐ芯を狙い、喉や舌に余計な力が乗らないようにします。
基本手順
-
リードの開きを軽く指で整えてから、先端より深めにくわえます。
-
少量の息で反応を確認し、次に一定圧で持続させます。
-
ギャーと聞こえる不定高さの鳴き音を安定して維持できるか観察します。
このとき、音量だけで良否を判断しないことが肝心です。発音の立ち上がり、持続中の揺れ、息に対する追従性など、複数の観点を併せて見ます。
クローで判断できること
クローは、リードの物理的条件と音響的性質を短時間で推定するための指標になります。具体的には、開きの適否、全体厚みや心材の残し具合、左右のバランス、息の入りやすさ、音程の取りやすさの傾向などが見えます。
強いクローは倍音の含有が多い場合があり、明るいが不安定になりやすい傾向が考えられます。逆にクローが弱い、あるいは出にくい場合は、息の通りが阻害され、重く感じやすい方向が想定されます。
以下は、状態別の早見表です。
| クローの状態 | 想定される主因 | 音の傾向 | 対処の方向性 |
|---|---|---|---|
| 全く鳴らない | 開き過大 または 全体が厚い | 息が入りにくい | 開きを整える 先端とハートの厚みを微調整 |
| ぴーのみ鳴る | 開き過小 クリップ状 | 小音量で軽いが伸びない | リードを休ませ湿度調整 チューブ側のわずかな開きを確保 |
| ギャーが強すぎる | 先端が薄すぎ 心材アンバランス | 明るいがピッチが下がりがち | 先端を触らず中腹の抵抗を確保し左右整え |
| 揺れが大きい | 左右差 わずかな捩れ | 音程が泳ぐ | スクラップで整面 湿度とセッティングを見直し |
表はあくまで方向づけであり、単独要因で決めつけず複合的に観察します。
クローと倍音の関係性
クローは基音成分が曖昧で、整数次倍音と非整数次倍音が複雑に含まれます。ギャーという雑音的要素が強いほど、倍音の量や分布が多く、管体装着後に音色は明るく、しかしピッチのコントロールが難しくなる傾向があります。
一方、倍音が少なすぎると、音の伸びや投射性が不足し、ダイナミクスの上限が低くなります。
観点の整理
-
倍音量が多い:明るさと投射性は得やすいが、音程が下がりやすい
-
倍音量が少ない:ピッチは取りやすいが、発音と響きが重くなる
-
望ましい状態:目的の音色と音程の両立点を個々の奏者で定義する
要するに、倍音の多少自体が価値判断ではなく、演奏目的に対してどの分布が合致するかが焦点です。
クローが鳴らない原因
クローが反応しない場合、開き過大やブランク厚、含水率の不整合、チューブ差し込み深度のズレなどが想定されます。先端を安易に薄くすると短期的に反応は出ますが、耐久性の低下や音程の不安定を招きやすく、根本解決になりません。
チェックポイント
-
乾燥し過ぎていないか:短時間の湿潤で反応が改善するか
-
チップの微小なバリ:スクレーパーで面を整える前に観察
-
ワイヤーや糸のテンション:わずかな調整で開きが安定するか
以上の点を踏まえると、まずは湿度と開きのリセット、次に中腹の抵抗設計を優先する手順が合理的です。
クローがうるさい時の特徴
クローがギャーギャーと強すぎる場合、先端が薄い、ハートが弱い、左右の厚さ差がある、といった要素が重なっていることが多いです。管体装着後は第2オクターブでピッチが下がる傾向が出やすく、口の圧で無理に持ち上げると疲労を招きます。
抑え方の考え方
-
先端は極力触らず、中腹から抵抗を補う
-
左右の厚みと刃先の平行を再チェック
-
息の角度をまっすぐにし、口腔容積の過度な拡張を避ける
これらのことから、鳴りの派手さよりもコントロールの余地を確保する調整が、実演での安定に結びつきます。
クローの音程とリード選定
クローの音程目安として、B♭付近を好む流派やC付近を基準にする考え方があります。どちらを基準にするかは、楽器の個体差、奏者の息圧、目指す音色によって最適点が変わります。最も大切なのは、選定時の基準を一貫させ、管体装着後のピッチ実測と結び付けて評価することです。
実用的な選定手順
-
クローの反応と安定性を短時間で評価する
-
管体でオクターブ跨ぎのロングトーンを行い、ピッチの推移を確認する
-
音色・レスポンス・耐久のバランスで採否を決める
基準を記録しておくと、製作や購入の再現性が向上します。
オーボエのリード クローの調整と実践

リードの開きとクローの影響
開きは、クローの反応と演奏時の息圧カーブを左右します。開きが大きすぎると息が逃げ、クローは出にくくなり、音量は出ても音程が下がりやすくなります。逆に開きが小さすぎると、クローはぴーと鳴りやすいものの、低音や強奏で破綻しやすくなります。
実務的な整え方
-
乾湿で変動する前提で、基準開きを写真やゲージで可視化
-
糸巻きとスクレープの相互作用を把握し、片方だけで解決しない
-
最後に息での最適点を確認し、過度な口の圧に頼らない
以上の点を踏まえると、開きは音量ではなく可動域の設計として扱うことが鍵となります。
リードの厚みとクローの関係
厚み配分は、クローの雑音成分と管体装着後の倍音分布を決めます。先端を薄くし過ぎるとクローは派手になりますが、ピッチが下がり口で支える比率が増えます。中腹とハートを適切に残せば、クローは過度に騒がず、演奏時の芯が出やすくなります。
具体的な配慮
-
先端は最小限の研磨で平面性を優先
-
中腹は息の受け皿となるため、滑らかな勾配を確保
-
ハートは左右対称性と連続性を重視し、局所的な凹みを避ける
要するに、厚みは「薄いほど良い」ではなく、役割ごとに残す設計思想が有効です。
第2オクターブとクローの課題
第2オクターブは、クローが強いリードで特に音程が下がりやすくなります。これは倍音構成と管体内の共鳴条件が影響し、息圧で引き上げる対応は疲労と発音の荒れを招きます。
実践アプローチ
-
リード側:中腹の抵抗を補強し、先端を触らずに安定化
-
奏法側:息のスピードを上げつつ量は抑え、口腔形状で持ち上げない
-
検証:A4以上の音でロングトーンし、チューナーの推移を記録
以上の点を踏まえると、リードと奏法を同時に最適化することで、上域のピッチが落ち着きます。
クローの安定性を高める方法
安定性は湿度管理、材質の選定、微調整の順で確保します。まずケース内の湿度を保ち、演奏前の水分管理をルーティン化します。次に、材の弾性と繊維方向の均一性を選別基準に加えます。最後にスクレープの微修正を行います。
小さな工夫
-
湿潤時間を固定し、吸水のばらつきを抑える
-
端面の毛羽立ちを極細紙で整え、気流の乱れを減らす
-
差し込み深度とコルクの密着を点検し、漏れを防ぐ
これらを積み重ねることで、クローは小音量でも安定し、現場での再現性が高まります。
オーボエにおすすめの音楽教室
オーボエをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のオーボエレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のオーボエレッスンを詳しく見る

オーボエ リードクローまとめ
まとめ
- クローはリード単体で反応と倍音傾向を把握する指標
- 目的は派手な鳴きではなく演奏時の制御性の確保
- 開きは音量ではなく可動域の設計として最適化
- 厚みは役割ごとに残し中腹とハートで芯を作る
- 第2オクターブは抵抗設計と息の速度で安定化
- 先端を安易に薄くせず耐久とピッチを両立する
- 左右対称と平面性が揺れや不安定の抑制に効く
- 湿度管理と吸水時間の固定で反応の再現性を向上
- 選定基準を記録し管体でのピッチ実測と結ぶ
- 倍音の多少は価値判断ではなく目的適合で考える
- うるさすぎるクローはピッチ低下の兆候になり得る
- ぴーのみの状態は開き過小の再点検を優先する
- 調整は先端より中腹とハートから順に整える
- 息の角度をまっすぐ保ち口腔形状に頼り過ぎない
- オーボエ リード クローの基準を一貫して運用する
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ