❕本ページはPRが含まれております
ヤマハ 歴代クラリネットという観点でモデルの流れを整理したい方に向けて、主要機種の登場年やシリーズごとの特徴を年代順にまとめます。
カタログ用語や設計の狙いを平易に説明し、同一シリーズ内の位置づけも理解できるように構成しています。初めて調べる方でも迷わないよう、読みやすさと網羅性の両立を心がけています。
この記事でわかること
- 主要モデルの発売年と年代ごとの位置づけ
- シリーズ名ごとの設計思想と違いの要点
- 同年代に併売された機種の関係性
- 選定や比較で注目すべき仕様の観点
ヤマハクラリネット 歴代の歩みを解説

引用:楽天
歴代の歩みを解説
1970年代のYCL-61から始まる展開
ヤマハのプロモデルとしてYCL-61が1972年に発売され、国産クラリネットの基盤づくりが本格化しました。素材はグラナディラを中心とし、安定した音程と堅牢なメカニズムを目指す設計が採用されています。
この時期の成果は、その後のカスタム系の設計思想につながり、上位機の登場に向けた土台となりました。
年表ダイジェスト(1970年代〜前半)
| 年 | モデル | 区分 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 1972 | YCL-61 | プロモデル | 安定性重視の基礎設計 |
| 1974 | YCL-81、YCL-85 | カスタム | B♭とAで上位志向を明確化 |
| 1979頃 | YCL-82 | カスタム | ラージボアで音色と投射を拡張 |
初期カスタムモデルYCL-81とYCL-85
1974年に登場したYCL-81(B♭)とYCL-85(A)は、プロユースに向けた高精度の音孔設計やキーワークのフィット感を特徴とします。
音色はクリアさと均質性の両立を意識したチューニングで、当時の国際的なピッチ事情に合わせた扱いやすさが評価されました。B♭とAを揃えることで、オーケストラでの持ち替えにも配慮したラインナップとなっています。
ラージボア仕様YCL-82の特徴
1979年頃に登場したYCL-82はラージボア仕様が特徴で、音量感や遠達性を高めた設計です。息を多めに入れても音程が揺れにくい方向性があり、広い会場でも輪郭が崩れにくい発音を狙っています。
吹奏感はやや抵抗少なめに感じられるセッティングで、音の立ち上がりが速い点も実演奏での強みとして捉えられます。
1980年代のCXとCSシリーズの登場
1984年にはカスタムのCX系(YCL-851、852)とCS系(YCL-841、842)が登場し、音色キャラクターを分化させました。一般にCXはふくよかで包容力のある方向、CSは輪郭と反応性を重視した方向を担い、選好や編成に応じた選択肢が広がりました。
設計面では音孔形状やベル内径、バレル設定などを組み合わせ、同じ素材でも異なる鳴り方を生み出しています。
シリーズ比較メモ
| シリーズ | 代表機種 | 傾向 | 想定シーン |
|---|---|---|---|
| CX | 851、852 | 豊かで厚みのある響き | ソロ、室内楽での存在感 |
| CS | 841、842 | 応答の速さと明瞭さ | アンサンブルでの輪郭確保 |
プロモデルクラリネット651や681の発売
同じ1984年にプロモデルのYCL-651(B♭)とYCL-681(E♭)が発売され、日常的な演奏現場で扱いやすい堅実な選択肢が整いました。
加えて、バスクラリネットYCL-621とアルトクラリネットYCL-631もラインナップされ、合奏での低音域を支える体制が強化されています。操作系の信頼性と調整の持続性が重視され、メンテナンス面も含めた総合的な使い勝手が向上しました。
ヤマハクラリネット 歴代モデルの進化

引用:楽天
歴代モデルの進化
SEやAEシリーズとその位置づけ
1986年にはSE(YCL-853、854)とAE(YCL-843、844)が登場し、上位機の方向性がさらに明確になりました。SEは深みと遠鳴りを意識した音作りで、低音域の厚みや中音域の滑らかさが要点です。
対してAEは芯のある明瞭なサウンドで、音程の安定とアーティキュレーションのしやすさが特徴になります。演奏現場の要求に応じて、表現力の幅か、操作性の軽さかという観点で選び分けが進みました。
ドイツベームクラリネット856と846
1987年のYCL-856(B♭)とYCL-846(A)は、ドイツの音色観に配慮した設計がキーワードです。ボアや音孔の最適化により、重心の低い響きと豊かな倍音を引き出し、分厚い合奏の中でも密度のあるサウンドを確保します。
キー配列やタンポ合わせの精度も追求され、ベーム式の運指を保ちながらドイツ志向の音色を志向する奏者に向けた提案となりました。
ラボシリーズIdealやFinesseの特徴
1992年にはラボシリーズとしてIdeal(YCL-951、952)とFinesse(YCL-941、942)が登場しました。研究開発の成果を迅速に反映するコンセプトで、音孔の微細なテーパーやバレル設定の見直しなど、応答と音程バランスを高次元で突き合わせた点がポイントです。
Idealは伸びや投射、Finesseは繊細なニュアンス表現に比重を置き、録音現場とホール実演の双方で選択肢が広がりました。
Virtuosoを含む1990年代のラインナップ
1993年にはVirtuoso(YCL-953、943)が追加され、ラボシリーズの系譜が充実しました。同年には主要カスタム各機種のⅡ系モデルがモデルチェンジし、精度や耐久性の向上が図られています。
1994年にはE♭クラリネットYCL-881が登場し、ピッコロ的な高音域の安定性と発音の速さが高められました。
さらに1996年のVシリーズ(YCL-852ⅡV、853ⅡV、842ⅡV、843ⅡV)は、鳴りの均質化と反応性の改善を狙ったアップデートで、音程のセンターがつかみやすいセッティングが採用されています。
1990年代前後の主要機種
| 年 | モデル | 区分 | メモ |
|---|---|---|---|
| 1992 | 951、952、941、942 | ラボ | IdealとFinesse |
| 1993 | 953、943 | ラボ | Virtuosoの追加 |
| 1993 | 851Ⅱ、852Ⅱ、853Ⅱ、854Ⅱほか | カスタム | モデルチェンジ |
| 1994 | 881 | E♭ | 高音域の機動性 |
| 1996 | 852ⅡV、853ⅡV、842ⅡV、843ⅡV | Vシリーズ | 均質化と反応性 |
2000年代以降のVmやArtistModelの展開
2002年頃にはエーラーシステムの国内展開が進み、選択肢の幅がさらに広がりました。2004年にはVmシリーズとしてSEVm/CSVm(A管はSEVmA/CSVmA)が登場し、息の通りと音の立ち上がりを洗練させています。
同年にIdealの系譜としてYCL-950Ideal(B♭)とYCL-940Ideal(A)も発売され、音色のしなやかさと遠達性の両立を狙いました。
2009年にはYCL-IdealG/IdealGAが追加され、音程安定のチューニングと中音域の密度感が強化されました。2013年には限定モデルのSEVmKF/SEVmAKFが登場し、素材選定やパーツ仕様に工夫を凝らした特別仕様が話題となりました。
2015年にはSE ArtistModel/SE ArtistModel Aが加わり、細部の工作精度やキー形状の最適化、音孔の再検討など、トップエンドとしての完成度を高めています。
2000年代以降の主な年表
| 年 | モデル | 区分 | 主なポイント |
|---|---|---|---|
| 2002頃 | エーラー管 | システム | 国内展開の拡大 |
| 2004 | SEVm、CSVm、SEVmA、CSVmA | Vm | 反応と遠達性の両立 |
| 2004 | 950Ideal、940Ideal | ラボ | 音色の柔軟性 |
| 2009 | IdealG、IdealGA | ラボ | 音程と密度の強化 |
| 2013 | SEVmKF、SEVmAKF | 限定 | 素材・仕様の特別設計 |
| 2015 | SE ArtistModel、SE ArtistModel A | カスタム | トップレンジの完成度 |
自宅に眠るサックスは楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていないサックスがあるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。
テナーサックスやアルトサックスなど、サックス全般の取り扱い実績も豊富なので安心です。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
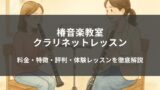
ヤマハのクラリネット 歴代まとめ
まとめ
- 1972年のYCL-61からプロモデルの基盤が確立
- 1974年のYCL-81と85でカスタム路線が明確化
- 1979年頃のYCL-82はラージボアで投射を強化
- 1984年のCXとCSで音色志向の選択肢が拡大
- 同年の651や681で実用性重視の系譜が整備
- 1986年のSEとAEで深みと明瞭さを分化
- 1987年の856と846はドイツ志向の設計を提案
- 1992年のIdealとFinesseで実験的成果を製品化
- 1993年のVirtuoso追加で表現幅がいっそう拡張
- 1994年の881でE♭管の機動性と安定性を向上
- 1996年のVシリーズで均質化と応答性を刷新
- 2002年頃のエーラー管展開で選択肢が多様化
- 2004年のVmとIdealで現代的な鳴りを追求
- 2009年のIdealGで音程と密度のバランスを改善
- 2015年のSE ArtistModelで完成度がさらに進化


