❕本ページはPRが含まれております
クラリネットの替え指とトリルを体系的に学びたい方に向けて、トリルとは何かから良く使うトリルの要点、替え指とトリルの一覧の見方、運指表の活用法まで、わかりやすい流れで解説します。検索で迷いやすい用語の整理と実践手順をまとめ、独学でも理解が深まるように構成しました。
この記事でわかること
- よく使われる替え指トリルの種類と特徴
- 運指表を使って最短で照合する手順
- 音程と音色を崩さない実践的なコツ
- 練習計画とつまずきやすい点の対処
クラリネット 替え指トリルの基礎知識

トリルとは基礎から理解する
トリルは主音とその上の二度の音を素早く往復する奏法です。クラリネットでは鍵盤楽器のように隣接した鍵を交互に打鍵するのではなく、管の開閉とサイドキーの組み合わせで音高を切り替えるため、通常の運指だとスムーズに動かせない箇所が出てきます。そこで、トリル専用の替え指を用いるのが一般的です。
拍の中心で揺れが均等に聞こえること、音価の最後に不自然な切れ目を作らないこと、息の流れを止めずに指だけを素早く動かすことが、聴感上の滑らかさにつながります。
また、曲や時代の様式によっては上の音からトリルを始める解釈もあるため、譜面上の指定や慣習を確認すると安心です。練習ではメトロノームに合わせ、音の粒立ちと周期の安定を優先して段階的にテンポを上げると効率的に整います。
良く使うトリルを整理する
クラリネットでは、右手サイドキーを中心に次のようなトリルが頻出します。
高いド⇔レは、ドの指で右手サイドキー上から2番目を素早くタップします。この運指は伸ばし音としては保持が難しく、トリルの速度と息のスピードが鍵となります。
高いド⇔レ♭は、右手サイドキー上から3番目と4番目を同時に押します。二つを同時に捉える指の角度が難所で、指先の肉を挟まない当て方を反復でなじませると安定します。
ラ⇔シは、ラの基本運指に右手サイドキー最上段を加えます。音程が上ずれやすいためテンポをやや速め、アンブシュアを一定に保つことで輪郭が整います。
ラ⇔シ♯(ド相当)は、ラの基本運指に右手サイドキー最上段と上から2番目を加えます。こちらは逆にわずかに低めに寄る傾向があるため、息のスピードを落とさず支えを強めに取ると良好です。
シ♭⇔ド♭(シ相当)は、右手サイドキー上から2番目で切り替えます。音程の不安定さが出やすく、短めで細かく揺らすアプローチが扱いやすいです。
シ♭⇔ドは中音域で使う半音トリルで、音色が曇りやすい帯域です。チューナーで通常運指とのピッチ差を確認し、息のスピードを高めて明度を確保します。
ファ⇔ソ♭には二通りが実用的です。ひとつはファの指で右手サイドキー上から3番目と4番目を同時に押す方法で、機動力に優れます。
もうひとつは運指表に載る一般的な替え指で、半音階を滑らかにつなぐ際に重宝します。どちらも場面に応じて選べるよう音程と音色の傾向を把握しておくと安心です。
替え指 トリル 一覧をチェックする
下表は頻出の替え指トリルを、操作と音程傾向の目安で整理したものです。実際の個体差やセッティングで結果は変わるため、チューナーでの微調整を前提に活用してください。
| トリル対象 | 出発音 | 到達音 | 主なキー操作 | 音程傾向の目安 | 実践メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 高いド⇔レ | ド | レ | 右手サイド上から2番目をタップ | やや高めに寄りやすい | 息速く、指の振幅を小さく |
| 高いド⇔レ♭ | ド | レ♭ | 右手サイド3番目+4番目同時 | 個体差が大きい | 指の角度で安定性が向上 |
| ラ⇔シ | ラ | シ | ラ運指+右手サイド最上段 | 上ずれやすい | テンポ速めで短周期に |
| ラ⇔シ♯(ド) | ラ | ド | ラ運指+サイド最上段+2番目 | 低めに寄りがち | 息の支えで補正しやすい |
| シ♭⇔ド♭(シ) | シ♭ | シ | 右手サイド上から2番目 | 不安定になりやすい | 短い揺れで明瞭に |
| シ♭⇔ド | シ♭ | ド | 中音域の替え指を使用 | 低めに出やすい | 息のスピードで明度確保 |
| ファ⇔ソ♭(方式A) | ファ | ソ♭ | 右手サイド3番目+4番目 | わずかに揺らぐ | トリル以外でも応用可 |
| ファ⇔ソ♭(方式B) | ファ | ソ♭ | 一般的な替え指(運指表参照) | 安定しやすい | 半音階の連結に有効 |
表の「方式B」は多くの運指表に記載のあるメジャーな方法です。場面のテンポやフレーズの方向でA/Bを切り替えると、音程と音色の折り合いが取りやすくなります。
運指表で確認できる指使い
替え指は機種やメーカーによるキー配置の微差で操作感が変わります。運指表ではサイドキーの段数や位置を記号や略号で示すため、使用モデルの表記規則を最初に把握すると照合が速くなります。
トリル専用の記号や「代替運指」欄が別枠で掲載されている場合は、該当ページを付箋やマーカーで素早く参照できるようにしておくと便利です。
同じ音でも、音色優先とピッチ優先で複数の選択肢が提示されることがあります。曲のテンポ、ダイナミクス、周囲の和声進行に合わせ、候補を実際に吹き比べて最適解を決めるのが現実的です。記録用に自分専用の補助表を作り、成功した組み合わせを譜面番号とともにメモすると再現性が高まります。
わかりやすい運指練習の工夫
練習は音を鳴らす前の準備から効率が変わります。まず、机上での空運指で「触れる位置」と「押す角度」を身体に覚え込ませると、実音練習で音程の揺れが減ります。次に、四分音符1本分の長さの中で均等な往復を作る練習に移り、テンポを段階的に上げます。
指と息の役割分担
トリル中は息が音量と音色の骨格、指が音高の切り替えを担います。息のスピードを一定に保ち、口の内側の形を急に変えないことが安定の土台になります。指は上下の移動距離を最小化し、キーの端を叩かずに面で捉える意識が有効です。
音程管理のルーティン
替え指はピッチが動きやすいため、通常運指の基準音と交互に鳴らして差分を耳とチューナーで確認します。録音して倍音の量感を聴き返すと、音色の曇りや尖りも把握しやすくなります。
クラリネット替え指トリルの具体的な指使い

半音階で使う替え指 トリル 一覧
半音階の動きはトリルと親和性が高く、特に中音域で登場頻度が上がります。シ♭⇔シやシ⇔ド、ミ⇔ファ、ファ⇔ソ♭は運指の切り替えが複雑になりやすい箇所です。先述のファ⇔ソ♭の二方式に代表されるように、替え指を使うことで指の往復距離を短くし、連結を滑らかにできます。
各半音の接続で優先したいのは、音程の「中心」がどこにあるかを耳で把握することです。例えばラ⇔シは上ずれ傾向、ラ⇔シ♯はやや低めといった癖を踏まえ、和声の構成音に寄せる形で補正します。
テンポの速いパッセージでは、全てを完全に合わせようとせず、音色の明瞭さと周期の均等を優先した方が音楽的な効果が高く聞こえます。
運指表を活用した学習方法
学習手順は次の三段階に分けると実用的です。第一に、運指表で候補を洗い出し、曲中で必要なトリルだけに印を付けます。第二に、候補を2〜3案に絞って基準音とのピッチ差と音色を比較します。第三に、実際のテンポと音量で試し、最も安定して再現できる案を採用します。
練習ノートを用意し、曲名、箇所、小節番号、採用した替え指、注意点を簡潔に記録しておくと、次回以降の準備が格段に速くなります。演奏環境やリードの状態で結果が変わるため、複数案を残しておく柔軟性も役立ちます。
良く使うトリルの注意点
替え指は便利である一方、音程と音色のブレが生じやすい側面があります。キーを強く叩くとノイズが乗り、息を弱めると音がやせます。息は一定の圧で前へ送り、指は最短距離で上下させ、キーに対して垂直に近い角度で当てると雑音が減ります。
右手サイドキーの同時押し(ド⇔レ♭、ファ⇔ソ♭の方式A)は、押し分けの曖昧さがピッチの揺れに直結します。指の腹を鍵の中心に置くイメージで、関節の位置を固定してからスナップを小さく効かせると分離が明瞭になります。
また、速さを求めるあまり周期が乱れると揺れが崩れて聞こえるため、テンポよりも均等性を優先して段階的に速度を上げると安定します。
初心者にもわかりやすい解説
初めて取り組む場合は、次のステップで進めると理解が進みます。
- 音価を保ってゆっくり往復し、均等な周期を体に入れます。口の形と息の圧を一定に保つことを意識します
- メトロノームを使い、四分音符1拍に2回、4回、8回と段階的に細分化します。各段階でブレが出ないことを確認します
- 実際のフレーズに当てはめ、拍頭やフレーズ終止での収め方を決めます。必要に応じて替え指をA/Bで切り替え、最も自然に聞こえる案を採用します
この流れで練習すると、技術的な要素が分解され、再現性の高いトリルが身につきます。加えて、録音して客観的に聞き返す習慣を作ると、息と指のバランスの偏りに自分で気づけるようになります。
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
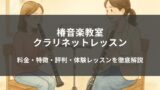
クラリネット替え指トリルの学び方まとめ
まとめ
- トリルは主音と二度上を均等に往復させる奏法
- 右手サイドキーの扱いが機動力の要となる
- ドからレのトリルは二番目サイドを素早く使う
- ドからレ♭は三番目と四番目を同時に押さえる
- ラからシは最上段サイド追加で上ずれを抑える
- ラからシシャープは低め傾向を息で補正する
- シ♭からシは不安定のため短周期で揺らす
- シ♭からドは音色曇り対策に息を速く保つ
- ファからソ♭は二方式を曲想で使い分ける
- 運指表で候補を洗い出し実音で比較する
- チューナーで通常運指との差分を可視化する
- メトロノームで周期の均等性を最優先にする
- 指は最短距離で動かしキーは面で捉えて押す
- 録音を活用し音程と音色の客観評価を行う
- 楽曲と環境に応じて複数案を準備して臨む


