❕本ページはPRが含まれております
クラリネットの初心者は難しいと感じやすく、最初に音が出ない場面で戸惑うことが多いです。とはいえ、息の方向と速さ、そして姿勢の整え方を理解すれば、安定した発音に近づけます。
この記事では、楽器の構造的な特徴から、息づかいのコツ、座奏と立奏の姿勢、力みを抜く工夫、ストラップや親指の負担軽減まで、つまずきやすい要素を体系的に整理します。練習の指針が明確になれば、初めての壁は越えられます。
この記事でわかること
- 息と姿勢の基礎を整理して音を安定させる
- 音が出ない原因を症状別に切り分ける
- 力みの解消とストラップ活用で負担を減らす
- 座奏と立奏のコツを理解して効率よく上達する
クラリネット 初心者が難しいと感じる理由とは

クラリネットの特徴と初心者の印象
クラリネットはシングルリード方式の木管楽器で、マウスピースとリードの隙間に素早い気流を通して音を鳴らします。縦型でリコーダーに似た見た目ですが、必要な息の速さと量は想像以上に大きく、やわらかい息では振動が起きにくい点が初心者にとってギャップになりやすいです。
運指はキーとトーンホールの組み合わせで成り立ち、手のフォームや指の曲げ方がわずかに崩れるだけでも音孔の密閉が甘くなり、音色や反応に影響が出ます。さらに、上下管のジョイントのねじれやリードの位置ズレなど、組み立て時の小さな誤差も発音を不安定にします。
以上の特性から、最初は難しく感じても不思議ではありませんが、息と姿勢の基礎を押さえると反応が一気に改善しやすく、初期のハードルは下がります。
初心者が音が出ないと感じる原因
音が出ないときは、原因を切り分けると解決が速くなります。代表的な症状と対処の目安を整理します。
| 症状 | 主な原因 | すぐ試す対策 |
|---|---|---|
| 空気だけ通る感じで鳴らない | 息の速さ不足、アンブシュアが甘い | 口角を軽く引き、息を速く細く入れる |
| ブーブーとこもる | リード位置のズレ、リガチャーの締め過ぎ | リード先端をマウスピースと面一に調整 |
| 高音がかすれる | 気流の方向が下がる、喉が詰まる | あくびの口内で喉を広げ、前上向きの気流 |
| 低音が鳴りにくい | 指孔の密閉不足、左手親指の穴の甘さ | 指腹で覆い直し、手首を内側に入れ過ぎない |
| すぐバテる | 肩や首の力み、息の回し方が非効率 | 肩を落として深く吸い、長音で配分を確認 |
原因の多くは息の速さと方向、アンブシュアの密着、指孔の密閉に集約されます。ひとつずつ検証し、変化の有無を音で確かめる流れが有効です。
息の使い方が安定しないときの対処法
狙いは、速く均一な気流を保つことです。腹部や肋骨周辺の広がりを意識して吸い、吐くときはお腹を固め過ぎず、一定の圧を保ちながら前方へ気流を送り込みます。喉は脱力し、唇は口角を軽く横に支えてリードを安定させます。
長音で身につける
1小節分をメトロノームに合わせて、一定の太さの音で伸ばします。録音して冒頭と終わりの音量差を確認し、息の配分をならしていきます。
アタックを整える
タンギングは舌先でリード先端付近を軽く触れて離すイメージです。息を先に流し始め、舌でオンにする順序を徹底すると、出だしの不安定が減ります。
気流の方向を固定する
顎を引き過ぎると気流が下がってこもります。譜面台の高さを目線に合わせ、首が前に出ない位置で息の通り道を確保します。息の速さは想像より速く、弱く長くではなく速く均一が鍵となります。
姿勢を整えることで演奏が楽になる
姿勢は吸気と気流の通り道を左右します。背骨を伸ばしつつ反らせ過ぎず、胸郭を上下左右に広げる意識を持つと、深い呼吸がしやすくなります。首は正面、顎は軽く引き、クラリネットは体に寄せ過ぎない角度で構えます。
| 姿勢の比較 | 座って演奏 | 立って演奏 |
|---|---|---|
| 重心 | 坐骨に均等、足は床全面 | 両足で肩幅、土踏まずで支える |
| 楽器角度 | 膝や譜面台に近づけ過ぎない | 体に寄せ過ぎず自然な前傾 |
| 呼吸 | 腹部と背中の拡張を感じやすい | 吸気量を確保しやすく持久性も上がる |
| 注意 | 猫背や首前出しを避ける | 反り腰と肩の持ち上げに注意 |
座奏でも立奏でも、共通して首と肩の脱力がポイントです。息の通り道が直線に近づくほど、少ない力で太い音に到達しやすくなります。
力を抜くことが上達の近道になる理由
過緊張は気流を細らせ、指の可動域も狭めます。握力で支えようとすると手首まで固まり、運指のタイミングが遅れます。脱力の起点は肩と首です。肩甲骨を下げ、肘をぶら下げるように構えると、手の力みが自然と抜けます。
アンブシュアは強く噛むのではなく、口角で支え、下唇はクッションとしてリードに当てます。力感は最小限に留め、息の速さで音量を作るほうが音色は安定します。ストラップの併用は、保持の不安からくる過緊張を減らす助けになります。
クラリネットが難しい初心者が克服する方法

初心者が克服する方法
楽器の重さを軽減するストラップの活用
ストラップは楽器の重量を体幹側に逃がし、右手親指の負担を軽くします。首掛け型、ショルダー型、ハーネス型があり、体格や持久時間に合わせて選べます。高さはマウスピースが自然に口へ届く位置に調整し、顎を突き出さない長さを基準にします。
ストラップを使うと、落とさないよう強く握る癖が減り、指先の可動性が上がります。長時間の練習でも姿勢の崩れが少なく、息の通り道の確保にもつながります。児童や小柄な奏者にも有効で、早期から安定した保持を身につけやすくなります。
親指への負担を減らすための工夫
右手親指は楽器の支点です。親指の当たる位置を少し外側にして、第1関節を軽く曲げると、骨格で支えやすくなります。指かけにクッションやカバーを使うと、局所的な圧迫感を緩和できます。
親指だけで支えようとせず、左手の触れ方やストラップの補助で荷重を分散します。親指の痛みが出るときは手首の角度も見直し、手の甲と前腕が一直線になるよう調整すると負担が下がります。
座って演奏するときに意識したい姿勢
椅子は深く座り過ぎず、坐骨で垂直に体を支えます。足は床全面に置き、譜面台は目線の高さへ。首が前に出て下向きになると気流が下がり、こもった音になりやすいです。
クラリネットは膝や譜面台に近づけ過ぎず、角度は体から適度に離して前へ。肩を下げ、肘を体側に寄せ過ぎないことで、指がスムーズに動きます。長音練習を挟みながら、前後左右のバランスが崩れていないか都度確認すると再現性が高まります。
立って演奏する際の正しい構え方
両足は肩幅で、重心は土踏まず付近に保ちます。骨盤を立て過ぎず、反り腰にならない範囲で背筋を伸ばします。譜面台の高さは目線に合わせ、顎を上げ下げしない位置に調整します。
楽器は体に寄せ過ぎず、気流の通り道がまっすぐになる角度を探ります。長時間の立奏ではショルダー型やハーネス型のストラップが安定しやすく、肩の持ち上げ癖の抑制にもつながります。
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
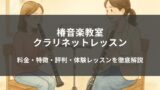
クラリネットが難しい初心者のためのポイント
まとめ
- 息は速く均一に保ち口角で支え気流の方向を安定させる
- 姿勢は背骨を伸ばし首を正面に向け気道を確保する
- 音が出ない原因はリード位置や指孔密閉を優先確認する
- こもる音はリードとリガチャーの調整で改善しやすい
- 高音の不安定は喉の開きと気流の前上方向で整える
- 低音の鳴りにくさは親指穴と指の覆い方を点検する
- 長音練習で息の配分と発音の再現性を高めていく
- タンギングは息を先に流し舌でオンにする手順を徹底する
- 力みは肩と首から抜き手首と指の自由度を取り戻す
- ストラップ活用で保持の不安を減らし運指を滑らかにする
- 親指の負担はクッションと手首角度で分散を図る
- 座奏は坐骨に均等な重心で譜面台は目線に合わせる
- 立奏は土踏まずで支え反り腰を避け息の通路を直線化する
- 練習ごとに姿勢と角度を微調整し最適解を記録する
- 基礎の反復と小さな改善の蓄積が上達の近道になる


