❕本ページはPRが含まれております
クラリネット リード 付け方で迷っている初心者の方に向けて、リード 素材の基礎から番号の選び方、開封直後や演奏前の状態の整え方、マウスピース上での高さの基準、リガチャーの種類や取付方法、留め具の締め加減まで、つまずきやすいポイントを一つずつ整理して解説します。
これから始める方も、自己流を見直したい方も、手順と判断基準を押さえることで安定した音と吹奏感に近づけます。
この記事でわかること
- リードの素材と番号ごとの特徴を理解できる
- 取り付け前の状態チェックと慣らしを学べる
- マウスピース上での高さと位置合わせが分かる
- リガチャーと留め具の正しい扱いと手順を身につける
クラリネット リード 付け方の基本

初心者が押さえる準備と注意点
演奏前は、手指を清潔にし、爪の角でマウスピースやリードを傷つけないよう意識します。作業は落ち着いて行うため、机上で視線の高さを合わせ、十分な明るさを確保します。リードケース、清潔な布、コルクグリスなどの基本アイテムを手元に置くと、無理な力をかけずに作業できます。
マウスピースはエボナイトなど傷がつきやすい素材が用いられているため、金属パーツの取り回しには配慮が必要です。焦らずに順序を決めて繰り返すことが、安定した結果につながります。
リードの素材の基礎知識
一般的なクラリネットリードは水辺に育つ葦の一種を加工した天然素材です。天然ゆえに個体差があり、気温や湿度で吸湿量が変わるため、毎日同一の吹奏感にならないことがあります。
開封直後は乾燥していることが多く、短時間の湿潤や穏やかな慣らしで柔軟性を引き出すと、発音が安定しやすくなります。天然素材は消耗品であるため、複数枚をローテーションして負担を分散させると寿命を伸ばしやすく、コンディションのばらつきも抑えられます。
番号の選び方と目安
リードの番号は主に厚さや硬さの目安を示し、数字が大きいほど抵抗感が増します。初学者は息の通りやすさを優先して低めの番号から始め、慣れてきたら段階的に上げていくと無理がありません。マウスピースの開きやフェイシング長との相性でも適正は変わるため、実際の吹奏で判断するのが堅実です。
| 番号の目安 | 吹奏感の傾向 | 合いやすい場面 | 調整のポイント |
|---|---|---|---|
| 2〜2.5 | 息が入りやすい | 初心者の基礎練習 | 高さを低めにし発音を安定 |
| 3 | 標準的な抵抗 | 基礎と合奏の両立 | 高さはごく薄く見える程度 |
| 3.5〜4 | 強めの抵抗 | 強い息圧や明るい音色 | 丁寧な慣らしと確実な固定 |
以上のように、息が苦しい、音が詰まる、ピッチが不安定といった兆候は、番号や取り付け位置の見直しサインになります。段差を感じる場合は、焦らず一段階戻して再調整すると判断しやすくなります。
状態の見極めと慣らし方
開封直後は、数分の湿潤で繊維を均一にし、短いロングトーンや静かなタンギングでならします。先端の反り、割れ、変色、側面の波打ち、裏面の歪みがないかを目視で確認します。
微細な反りは取り付け後の位置合わせである程度吸収できますが、明確な欠けや大きな歪みは演奏性に影響しやすく、別の個体へ切り替える判断が妥当です。ローテーション管理では、日付と印象を簡単に記録すると再現性が上がり、選別の精度が高まります。
マウスピースとの相性の考え方
同じ番号のリードでも、マウスピースの開きやフェイシングによって体感は大きく変わります。開きが大きいモデルでは、やや硬めのリードで息の支えを得る選択が考えられ、開きが小さいモデルでは柔らかめで反応を優先する判断がしやすくなります。
相性を検証する際は、音量だけでなく、低音域の発音、跳躍時の反応、ピッチの安定、同一息圧での音色変化を指標にすると、単なる吹きやすさに偏らない評価ができます。
クラリネット リード 付け方の手順

高さの合わせ方と基準
リードの先端とマウスピース先端の位置合わせは、取り付け工程の要です。一般的には、マウスピースの先端がごく薄く一筋だけ見える高さに設定すると、息の入りと反応のバランスがとれます。先端が飛び出すと息の流れを妨げ、逆に下がりすぎると音の立ち上がりが鈍くなります。
視線と角度のコツ
装着は必ず目線と同じ高さで行い、上下左右のズレを視覚的に確認します。斜めから覗くと錯視が生じ、先端合わせが不正確になりがちです。明るい環境で、先端の輪郭がはっきり見える位置関係を保つと微調整が容易になります。
ズレたときの微調整
上下の高さを決めたら、左右のセンターも確認します。リードの下部エッジとマウスピースのレールの見え方が左右均等になるよう指腹で軽く押さえ、わずかに滑らせるイメージで修正します。力を入れすぎると先端を欠く恐れがあるため、最小限の圧で操作します。
リガチャーの種類と選び方
リガチャーは大きく順締め、逆締め、紐タイプに分けられ、固定方法や音響傾向が異なります。順締めは扱いやすく、逆締めは視認性や手元の感触が好みで選ばれます。
紐タイプは接地の柔軟性が高く、細かな当たりの調整がしやすい一方で、一定の慣れが求められます。いずれも、マウスピースの形状に適合するサイズを選ぶことが前提です。
メンテナンスとチェックポイント
繰り返しの着脱で金属疲労やネジの緩みが生じることがあります。ネジのかみ合わせ、左右の均等性、パッドや当たり面の変形を定期的に点検します。
演奏中にカタカタとした雑音が出る場合、締め不足や部品の緩みが疑われます。異常を感じたら無理に使用を続けず、部品交換や別個体の使用に切り替えるとトラブルを避けられます。
取付方法の手順を整理
取り付け順は、リードを先に位置決めし、その後にリガチャーをかぶせて固定する流れが扱いやすいです。マウスピース表面は傷がつきやすいため、金属部品を先に動かすよりも、薄いリードを基準に位置合わせする方がリスクを抑えられます。
手順の流れ
- リードを軽く湿らせ、先端と側面の歪みがないか確認します
- マウスピース先端に対して高さを合わせ、左右のセンターを整えます
- リガチャーをそっとかぶせ、設計上の目印(溝や線)があればその付近に下端を合わせます
- 留め具のネジを上下交互に少しずつ締め、最終的な位置を微調整します
この一連の流れを一定の手順として定着させると、短時間でも安定した取り付けが再現でき、練習や本番前の準備が効率化します。
留め具の締め加減と調整
留め具はキツすぎても緩すぎても不具合が出ます。緩いとリードが動いてしまい、ビリつきや雑音の原因になります。過度に締めるとリードを圧迫して振動を阻害し、音が詰まった印象になりやすく、マウスピースの表面を傷つける恐れもあります。
上下にネジがある場合は、均等に段階的に締めていき、最後は小さな抵抗を感じたところで止め、試し吹きで反応とピッチを確認します。必要に応じて四分の一回転単位で微調整すると、音色と吹奏感の折り合いを見つけやすくなります。
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
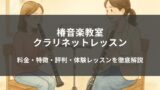
クラリネットのリード 付け方まとめ
まとめ
- 天然素材の特性を理解しローテーションで管理する
- 番号は息の入りと抵抗の折衷で段階的に選ぶ
- 取り付けは視線の高さで先端位置を正確に合わせる
- 先端はマウスピースが薄く見える程度に設定する
- 左右のセンターはレールの見え方で均等を確認する
- リガチャーは順締め逆締め紐の特徴を把握して選ぶ
- マウスピースの目印があれば下端位置合わせに活用する
- 取り付け順序を固定化して短時間で再現性を高める
- 留め具は上下交互に締め微小回転で最終調整する
- ビリつき雑音は緩みや部品異常のサインとして捉える
- 開封直後は短時間の湿潤と穏やかな慣らしを行う
- 苦しさや詰まりは番号や高さ再調整の合図と考える
- 練習では低音の発音と跳躍の反応も評価指標にする
- 記録を取りコンディションと印象を可視化して選ぶ
- 安定した手順と基準が音色とピッチの再現性を支える


