❕本ページはPRが含まれております
クラリネット の アンブシュアは、音程や音色、発音の安定に直結する基本要素です。作り方が曖昧なままだと、初心者ほど下唇やマウスピースの位置、使う筋肉の方向性を迷いやすく、口を適切に閉じる感覚や顎の形、息の速度も定まらず、すぐに疲れを感じてしまいます。
本記事では、理想に近づくための具体的な手順とチェックポイントを体系的に解説し、迷いを一つずつ解消していきます。
この記事でわかること
- 下唇とマウスピースの関係を理解し安全にセットできる
- 口周りの筋肉と顎の使い分けで音色を安定させられる
- 息の方向とスピードを整えて発音と音量を調整できる
- 疲れを抑える練習設計で理想の形を持続できる
クラリネットのアンブシュアを正しく理解する

アンブシュアを正しく理解する
アンブシュアの基本的な作り方の流れ
アンブシュアは、下唇を軽く巻いて下の歯を覆い、マウスピースを適切な深さでくわえ、笑顔に近い頬の引き上げで口腔内を狭め、口周りの筋肉で包み込む手順で整えます。下の歯が直接リードに触れない程度に下唇をかぶせ、上の歯はマウスピースの上面に安定して当てます。
顔は正面を保ち、首を曲げて楽器に近づかないようにします。右手親指やストラップの長さで、マウスピースが自然に口元へ来る高さに調整すると、息の通りが整いやすくなります。最終的には、噛むのではなく、口輪筋を中心とした周囲の筋で包むことが鍵となります。
チェックポイント
下唇が巻き過ぎて硬い部分が当たっていないか、マウスピースが浅過ぎて音量が出にくくないか、深過ぎて音が開いたりリードミスが増えていないかを、ロングトーンと音階で確認します。
初心者が意識すべきアンブシュアの基礎
初心者は、まず再現性を高めることに集中します。同じ手順で同じ位置にセットできれば、音のムラは確実に減ります。鏡で正面を確認し、下唇の巻き量、マウスピースの見える量、上の歯の位置、頬の引き上げ具合を毎回そろえます。
さらに、チューナーやメトロノームを使い、ロングトーンで音程と響きの変化を観察すると、日々の微調整がしやすくなります。短時間でも高頻度の練習を積み、口周りの持久力を少しずつ育てる設計が有効です。
下唇の位置とリードへの当たり方
下唇は赤い柔らかい部分がリードに触れる程度に巻き、硬い部分が当たらないようにします。巻き過ぎると振動を阻害し、巻きが浅いと歯が触れて雑音やリードの損傷につながります。理想は、リード振動を妨げずにクッションとして支える状態です。
息を入れたときに、音の立ち上がりがなめらかでノイズが少ないなら、当たり方は適正だと考えられます。低音から中音、強弱を変えながら当たり具合を試すと、最適点を見つけやすくなります。
マウスピースをくわえる際の注意点
マウスピースの深さは音量、反応、音色に影響します。浅過ぎれば音量が不足しやすく、深過ぎれば音が開いてコントロールが難しくなります。
顔は正面、首はまっすぐを維持し、楽器側を顔に合わせる意識で位置を決めます。ストラップは長過ぎると首が折れ、息の通りが悪くなるため、口元に自然に届く長さに整えます。
| くわえ方の深さ | 主な傾向 | 起こりやすい症状 | 目安となる改善策 |
|---|---|---|---|
| 浅め | 音量小さめ・反応速い | ピッチ高め・音が薄い | 少し深くして息の量を増やす |
| 適正 | 音量と反応のバランス | 安定した音程と発音 | 現状維持で息の方向を確認 |
| 深め | 音が開く・コントロール難 | リードミス増加 | 少し浅くし口周りで包む |
以上の目安をロングトーンやタンギングで検証し、演奏目的に合わせて微調整すると適正点が定まります。
アンブシュアを支える筋肉の使い方
噛む力ではなく、口輪筋や頬の引き上げによる包み込みを軸にします。笑顔に近い表情で頬を上げると口腔内が狭まり、細く速い息を通しやすくなります。顎は下方向へ軽く張る意識を持ち、梅干し状のしわが出ない状態を保ちます。
練習では、短時間のアイソメトリック保持(無音でアンブシュアをキープ)と、ロングトーンでの持続を組み合わせ、過不足のない緊張感を体に覚えさせます。強く噛む必要がないので、上の歯の接地は安定感のため、下は包んで支えるという役割分担が明確になります。
クラリネットのアンブシュアを安定させるコツ

安定させるコツ
マウスピースを噛まずに口を閉じる工夫
閉じる感覚は、縦に噛むではなく、周囲から均一に包むイメージが適しています。まず、上下の歯の圧力をゼロに近づける意識を持ち、上歯はマウスピースを支えるだけ、下は下唇越しに触れない状態をキープします。
唇の四方から軽く引き寄せ、空気が漏れないシールを作ると、息のロスが減り発音が揃います。両端から息が漏れる場合は、口角の赤い部分をわずかに内側へしまうと閉鎖が改善します。
練習では、ppからffまでクレッシェンドしながら密閉感を崩さずに吹けるかを確認すると、実用的な閉じ方が身につきます。
顎の形が演奏に与える影響
顎を膨らませたり丸めたりすると、音色が曇りやすく、リードの動きを妨げます。下顎を下方向に軽く張って平らに保ち、必要に応じてほんのわずか前に出すと、梅干し状のしわが出にくくなります。
頬を上げる筋活動と組み合わせると、口腔形状が安定し、音の芯が明瞭になります。鏡で顎先のラインを確認し、音の立ち上がりやピッチの安定と相関を観察すると、微調整の方向が掴みやすくなります。
息のコントロールで音色を整える
クラリネットは細く速い息でリードを効率よく振動させます。息の方向はやや下向きを意識すると、音程が安定しやすく、雑音も減ります。
ブレスは胸部だけでなく下腹部のサポートを使い、吐き始めのスピードを一定に保ちます。ロングトーンで息の速さを段階的に変え、音色変化のポイントを記録しておくと、本番での再現性が高まります。
スタッカートでは息を止めず、舌先でリードを軽くタッチする感覚を維持すると、発音が揃いやすくなります。
演奏中の疲れを防ぐための練習方法
疲れの主因は、筋力不足と過剰な緊張の二つに分けられます。前者には、短いセッションを複数回に分ける分割練習が有効で、1セットのロングトーンや音階を終えたら休息を挟み、回数で総量を稼ぎます。
後者には、噛む力を抜くチェックを随時行い、包む力のみで保持できているかを確認します。アンブシュア保持ドリル(無音で30秒保持→30秒休息を数セット)を取り入れると、持久力が着実に伸びます。
力みが出たら、いったん深呼吸し、口角だけを軽く上げ直して再セットすると、不要な緊張をリセットできます。
自分に合った理想のアンブシュアを探す
骨格や出したい音のイメージは人それぞれです。基本原則を守りつつ、音色、反応、音程の三要素を観点に微調整を進めます。具体的には、マウスピースの深さ、下唇の巻き量、頬の引き上げ、息の角度を一つずつ変え、録音とチューナーで結果を比較します。
場面により、ソロではやや深めで豊かな響き、アンサンブルでは適正深さで混ざりやすい音といった使い分けも現実的です。継続的な検証で、自分の理想に最短で近づけます。
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
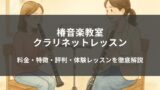
クラリネットのアンブシュアまとめ
まとめ
- 下唇は柔らかい部分で支え硬い部分は当てない
- マウスピースは浅過ぎず深過ぎず適正点を探る
- 噛まずに口周りで包み息漏れを抑えて密閉する
- 顎は下へ軽く張り梅干し状のしわを避けて保つ
- 頬を上げ口腔を狭め細く速い息を通しやすくする
- 息の方向はやや下向きで音程と立ち上がりを安定
- ロングトーンで音色と当たり方の最適点を確認する
- 分割練習と休息で持久力を育て疲れを抑えていく
- ストラップ長を整え首を曲げず自然な姿勢を保つ
- 口角を軽く内側へしまい両端の息漏れを防止する
- 上歯は支え下は包む役割分担で振動を妨げない
- 目的に応じて深さを調整し響きと混ざりを最適化
- 録音とチューナーで再現性を検証し改善を継続
- 表情筋のバランスを整え過剰な緊張を取り除く
- 基本原則の上で微調整を重ね理想へ近づけていく


