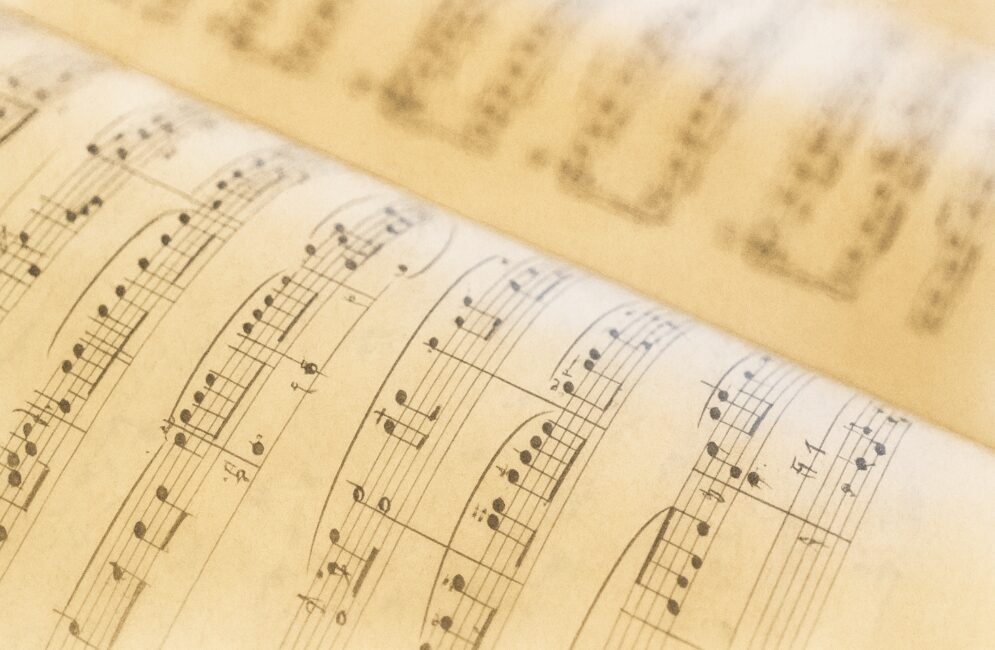❕本ページはPRが含まれております
ユーフォニアム 楽譜 読み方で検索すると、ヘ音記号とト音記号の違いや移動ドと実音の整理など、最初に迷いやすいポイントが次々に現れます。どちらで読むべきか、ブラスバンドや吹奏楽の譜面をどう解釈するか、練習では何から着手するかなど、判断がつきにくい場面が多いはずです。
本記事では、仕組みから練習までを順に整理し、読み替えの混乱を減らしながら演奏に直結する知識と手順を提供します。初心者でも段階的に理解できるよう、具体例と練習メニューを明確に示します。
この記事でわかること
- ヘ音記号とト音記号での読み方の整理
- 移動ドと実音読みの使い分けの基準
- 日々の練習で定着させる手順とコツ
- 用途別の教則本の選び方と活用法
ユーフォニアムの楽譜の読み方の基本を理解する

楽譜の読み方の基本を理解する
楽器の調性と記譜の調性の違い
ユーフォニアムはB管の金管楽器で、楽器の主音はシ♭に相当します。一方で、一般的なヘ音記号の譜面はinCとして記譜され、ピアノ譜と同じ実音読みで解釈します。ここで生じやすい混乱は、楽器の調性と譜面上の記譜の調性が一致しない場面があることです。
ヘ音記号では実音読み、ト音記号ではB管の移調記譜(記譜音から長二度上で書かれ、鳴る音は長二度下かつ1オクターブ下)という慣習が存在します。この違いを前提として、どの譜面を手にしているかを最初に確認する姿勢が読み間違いを減らします。
移動ドで楽譜を読む仕組み
移動ドは、各楽器の主音をドとみなして読む方法です。B管のユーフォニアムではシ♭をドとして読み進めます。運指や音の位置関係を早く体に入れたい初心者に適しており、指と音名の対応が直感的になります。
利点
・運指の習得が速く、合奏参加の初期段階で役立ちます
・調が変わっても相対的な位置関係で対応できます
注意点
・実音とのズレが生じ、ソルフェージュや他楽器との合わせで混乱を招くことがあります
・長期的には実音との接続を補うトレーニングが必要です
以上の点から、初学段階では移動ドで入り、耳と理論を育てる段階で実音との橋渡しを図る流れが効果的と考えられます。
実音で楽譜を読む際の特徴
実音読みは、譜面に書かれた音をそのままの高さで認識する方法です。ヘ音記号のユーフォニアム譜は基本的にinCで書かれるため、ピアノと同様に実音で読めます。ピアノ経験者や音感トレーニングを進めたい学習者に向いています。
適した学習者・場面
・ピアノやソルフェージュの経験があり、音高の直接的な認識に慣れている人
・アンサンブル全体の和声感や音程感を正確に把握したい場面
習得のコツ
・五線上の位置と音名を確実に一致させ、運指は別個に暗記します
・チューナーやキーボードと併用し、視覚と聴覚の一致を高めます
要するに、実音読みは合奏での整合性や理論理解を強化し、長期的な基盤づくりに向いています。
ヘ音記号とト音記号の読み方の違い
ユーフォニアムの譜面は主にヘ音記号ですが、ト音記号で書かれるケースもあります。両者の違いを下表に整理します。
| 記号 | 記譜の調性 | 実音との関係 | よく使われる場面 | 読み替えのポイント |
|---|---|---|---|---|
| ヘ音記号 | inC | 書かれた通りに鳴る | 吹奏楽、一般的な教則本 | ピアノ譜と同様に実音で読む |
| ト音記号 | inB | 記譜音より長二度下で鳴り、実際はさらに1オクターブ下 | ブリティッシュブラスバンド、難易度の高いソロ | B管トランペットの読み方に準じつつ、実音は1オクターブ低く捉える |
この対応を覚えておくと、初見でト音記号が出てきても混乱が減ります。まず冒頭やパート名に目を通し、どちらの記号か、移調指定があるかを確かめる手順が有効です。
吹奏楽やブラスバンドで使われる楽譜
吹奏楽ではユーフォニアムはヘ音記号inCが主流で、合奏全体の調性把握がしやすい構成です。一方、ブラスバンド文化圏ではト音記号inBが一般的で、金管群が共通の読み方でそろうため、移調の統一性が得られます。
下表は編成と記譜の傾向を比較したものです。
| 編成 | 記譜の傾向 | 学習上の焦点 |
|---|---|---|
| 吹奏楽 | ヘ音記号inC中心 | 実音読みで和声感を育てる |
| ブラスバンド | ト音記号inB中心 | B管読みと音域の体感を統一する |
所属団体の慣習に合わせつつ、どちらの記号にも対応できる基礎力を育てると、貸譜やソロ譜の違いにも柔軟に対応できます。
ユーフォニアムの楽譜の読み方を上達させる練習法

ユーフォニアムの楽譜の読み方を上達させる練習法
呼吸法とバズィングの基礎練習
演奏の土台は呼吸と唇の振動です。まずは静かな姿勢で下腹部まで空気を運ぶ意識を持ち、2拍または4拍で吸ってスムーズに吐き出す練習から始めます。マウスピースのみでのバズィングでは、過度な力を避け、均一な息の流れで明瞭な音高を保ちます。
効果的な流れは、呼吸法で息の通り道を整える→マウスピースでバズィング→楽器装着で同じ響きを目指す、の順です。メトロノームを用い、吸う拍も決めておくと再現性が高まります。息の速度と方向を安定させられれば、後続のロングトーンやリップスラーがぐっと容易になります。
ロングトーンで音を安定させる方法
ロングトーンは音色と音程の要です。テンポ50〜60で2拍吸い、中央のFを2拍伸ばす練習から始めると、息の準備と発音を落ち着いて整えられます。慣れてきたら他の音にも広げ、音量やアタックの種類を変えながら響きを観察します。
持続中は、息の支えと口形のバランスを微調整し、音程が上下に漂わないよう耳を使います。同じテンポ設定で日々記録すると、発音の均質性や持続時間の伸びが見える化され、改善点が明確になります。
タンギングを取り入れた練習メニュー
発音の明瞭さはタンギングで養われます。やりやすい音(中央のFやチューニングBなど)から、二分音符、四分音符、八分音符へと段階を踏み、テンポ60〜80で整えていきます。舌は当てるというより離す感覚で、過度な力みを避けると気流が途切れません。
半音階で上下に移動しながら、フレーズの終わりを全音符で伸ばして落ち着かせると、響きの質を確かめやすくなります。音価が短くなっても息の柱を崩さないことが、速いパッセージへの入り口になります。
リップスラーで柔軟な音を作るコツ
リップスラーは同じ運指のまま、息圧とアンブシュアの微調整で音高を変える練習です。四分音符や二分音符で、テンポ50〜60を基準に、上行と下行を均等に行います。上がりにくい場合は一度タンギングを入れて音の位置を確認し、再びスラーでつなぐと安定します。
音の切り替えで顎を大きく動かさず、口角と舌位のコントロールで微細な変化を作ると、スムーズな音列が得られます。半音ずつポジションを移し、息の方向は常に前方へ保つ意識が鍵となります。
音階練習で譜読みをスムーズにする
音階は譜読みを楽にし、指と耳の対応を整理します。長音階から始め、調号と音の並びを体に入れます。各調で上行下行を均等に行い、音域は無理のない範囲から徐々に拡大します。
テンポ設定は安定を最優先し、指回しよりも均質な音色と音程を重視します。音階の定着は初見力にも直結し、合奏での読み替えストレスを軽減します。慣れたら三度進行やアルペジオを加え、調性感を多面的に養います。
教則本を使った効率的な学習法
目的に合わせて教則本を選ぶと、練習の方向が明確になります。代表的な書籍と特長をまとめます。
| 書名 | 想定レベル | 主な内容・狙い |
|---|---|---|
| 朝練ユーフォニアム | 初心者 | 呼吸・バズィング・ロングトーン・音階など基礎網羅 |
| アーバン金管楽器教則本 | 初中級〜 | 豊富な練習曲と基礎、調性感とフレーズ感の強化 |
| The Remington Warm-Up Studies | 中級〜 | 音作り、持続音、充実したリップスラー |
| TECHNICAL STUDIES | 初級〜上級 | 息と唇のコントロール、音域拡張、細かな連結 |
| LIP FLEXOBILITIES | 初級〜上級 | リップスラー特化、段階的に難易度上昇 |
活用のポイントは、毎日のルーティンに小分けで組み込むことです。たとえば、呼吸とバズィング、ロングトーン、リップスラー、音階、技術課題の順に15〜30分ずつ配分し、曜日で重点を入れ替えます。記録を残し、音域や持続時間、テンポの目標を更新していくと、学習曲線が可視化されます。
おすすめの音楽教室
「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。
全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」
\無料体験レッスン実施中/
シアーミュージック公式サイトはコチラ
ユーフォニアムの楽譜の読み方まとめ
まとめ
・ユーフォニアムはB管でもヘ音記号は実音で読む
・ト音記号はinBで記譜され実音は長二度下で鳴る
・最初に譜面の記号と移調指定を必ず確認する
・移動ドは運指習得が速く初心者の導入に向く
・実音読みは和声感と合奏での整合に直結する
・呼吸とバズィングで息の流れを先に整える
・ロングトーンは音色と音程の土台を作り出す
・タンギングは舌を離す意識で気流を保つこと
・リップスラーは同運指で息圧と口形を制御する
・音階練習で調号理解と指回しを同時に鍛える
・吹奏楽はヘ音記号中心で実音読みが基本となる
・ブラスバンドはト音記号中心でB管読みを使う
・教則本は目的別に選び短時間で継続利用する
・練習は記録を取り小さな達成を積み上げていく
・ユーフォニアム 楽譜 読み方は基礎の反復で定着する
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ