❕本ページはPRが含まれております
マーチング ユーフォニアム 持ち方について、正しい構えや左手での支え方、移動時の安定方法、そして音がこもる悩みを減らす呼吸とアンブシュアの考え方まで、実践ですぐ役立つ要点を整理して解説します。
基礎から応用まで順に読み進めることで、姿勢や楽器の角度、息の使い方を一貫して整え、柔らかく響く音色に近づけます。部活や一般バンドの現場でも再現しやすい手順を採用し、フロントユーフォニアムの扱い方やウェストポーチなどの補助アイテムの使いどころも具体的に示します
この記事でわかること
- 正しい姿勢と左手での保持の要点を理解
- 移動を伴う演奏での安定化テクニック
- 音がこもる原因と改善の手順を把握
- フロントユーフォニアム運用の注意点
マーチングでユーフォニアムの持ち方の基本解説

持ち方の基本解説
ユーフォニアムの重さと特徴を理解
ユーフォニアムは一般的に約3.5〜5kgの重量があり、重心は主管とベルの接合部付近にあります。この重心特性を踏まえると、支点となる左手の位置と前腕の角度を一定に保つことが安定の鍵になります。
ベルはやや斜めに構え、視界を遮らない角度に保つと姿勢が崩れにくく、音の投射も安定します。右手はピストン操作に専念し、握力で支えようとせず、力みを最小化することで細やかなフィンガリングを維持できます。
太ももに楽器全体を預けると猫背を誘発しやすいため、長時間の練習では特に避けると良好なフォームを保てます。
正しい姿勢と猫背を防ぐポイント
脊柱を自然なS字に保つため、胸郭は縦方向に拡がる意識を持ち、肩は下げて首周りを緩めます。頭部は前に突き出さず、あごを軽く引いて視線は水平を保つと呼吸の通り道が確保されます。
座奏のときは骨盤を立て、椅子の座面に坐骨で乗る感覚をつかみ、脚は床全面で支えます。立奏や移動を伴う場面では、足幅を肩幅程度にして体幹で重さを受け、上半身だけでバランスをとらないことが姿勢維持に直結します。
頭とマウスピースの位置関係
顔を楽器に近づけるのではなく、楽器を顔に合わせにいく意識を持つと首・背中への負担が減り、アンブシュアの再現性が上がります。
左手で抱え込む安定した持ち方
左手は楽器の胴を包み込むように配置し、前腕と本体の接触面を広くとります。肘を身体の前方に張り出しすぎると肩に負担が集中するため、体側に近い位置で支えると疲労が分散されます。
左手親指は可動部に干渉しない位置で軽く固定し、手のひら全体で重さを受けると支持点が安定します。こうした保持が安定すると、右手は軽い力でピストンを操作でき、テンポが速い曲でも運指と音質の両立がしやすくなります。
腰や腕に負担を減らす工夫
長時間の練習や本番では、保持の微調整が体の負担を左右します。ベルト位置をやや上に設定して胴回りで重さを受け、骨盤の前傾を保つと腰が楽になります。肩を上げて保持し続けると僧帽筋が緊張しやすいため、肩は自然に下げ、脇に適度なスペースを確保します。
休憩ごとに握り直しや肩回しを行い、血流を促すと疲労の蓄積を抑えられます。必要に応じて軽量のクッションを膝上に挟む方法もありますが、頼り過ぎず、左手と体幹で支える基本形を日常的に鍛えることが再現性につながります。
小物の活用と注意点
クッションやパッドは接触面積を増やし安定に寄与しますが、角度が固定されすぎると音程や発音に影響する場合があります。使う場合は、日々の基礎練で角度の再現性を確認しながら調整します。
マーチング用フロントユーフォニアムの扱い方
フロントユーフォニアムはベルが前方を向く設計で、取り回しはトランペットに近いものの、重量は明らかに大きくなります。肘は過度に張らず、胸郭の拡がりを妨げない範囲で前方に配置します。手首は真っ直ぐを保ち、握り込みすぎないことで循環を妨げず指の独立性を確保します。
| 項目 | 通常ベル上向き | フロントユーフォニアム |
|---|---|---|
| 重心感 | 体幹寄りで安定 | 前方へ流れやすい |
| 構え角度 | ベルをやや斜め上 | 地面と平行を基準 |
| 体への負荷 | 左手と体幹中心 | 前腕と肩の負担が増えやすい |
| 対応策 | 左手面で支える | 肘の位置固定と体幹補助 |
| 音の投射 | 上方に拡散しやすい | 前方へ指向性が高い |
この特性を理解し、体幹で前方へのモーメントを受け止めることが操作安定の近道です。練習では短時間の反復でフォームを固め、疲労により角度が下がらないよう鏡で確認すると精度が上がります。
ウェストポーチを活用したサポート方法
移動を伴う演奏では、楽器下部を腰付近に軽く当てて揺れを抑える方法が有効です。ウェストポーチや幅広ベルトを装着すると接触面が増え、上下動の吸収に役立ちます。強く押し当てると音程や発音が不安定になる場合があるため、あくまで動作のガイドとして軽接触に留めます。
固定具に頼り切らず、左手と体幹で支える意識を並行して養うと、舞台や屋外など環境が変わっても再現性を維持できます。
実践で役立つマーチングでユーフォニアムの持ち方
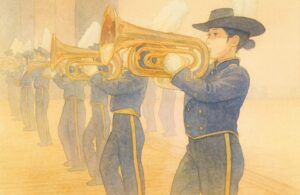
実践で役立つマーチングでユーフォニアムの持ち方
移動中も安定する構えの工夫
歩幅と歩調を一定にし、体幹の上下動を抑えると保持が安定します。足の接地はかかとからフラットに移行し、上半身は頭頂から引き上げる感覚で振れを最小化します。
方向転換やステップの大きい動作では、楽器下部を腰に軽く当ててモーメントを受け、肘の角度を崩さないよう意識します。視線は水平を保ち、譜面や指揮への注視で頭が前に出ないよう気をつけると、呼吸路が確保され音の立ち上がりが整います。
息の使い方と音がこもる原因
音がこもる主因は、唇や口角の締め過ぎによって口腔内の容積が狭まり、息の流れが滞ることにあります。高音や大音量を無理に出そうとすると口周りが硬直しやすく、振動が抑制されてしまいます。
改善には、歯を噛み締めず上下にわずかな隙間を確保し、舌はリラックスさせて息の通り道を広げます。息のスピードを上げる際も、喉を締めず腹圧で支えると、音程と音色が安定しやすくなります。
口腔内の空間を保つコツ
母音のうちオやウを軽くイメージすると口内が縦に開きやすく、息の直進性が高まります。アンブシュアは必要最低限の密着に留め、息で音高をコントロールする発想が有効です。
柔らかい音を出す吹き方のコツ
柔らかい音色に近づくには、息を速く細くするだけでなく、一定で滑らかな流れを維持することが要点です。アタックは舌先で軽く始動し、過度な舌圧を避けると立ち上がりが丸くなります。
マウスピース位置は唇の中央に安定させ、圧で押し付けないことで振動が保たれます。フレーズ全体のダイナミクスを先に設計し、山と谷を明確にすると、響きが整い濁りが減ります。
ロングトーンとスラーの活用
ロングトーンで音量一定の持続を養い、スラー練習で息の連続性を体得します。記録用にスマートフォンで録音し、ノイズやにごりの有無を客観的に確認すると改善点が見つけやすくなります。
プロ演奏を参考にした音色イメージ
理想的な音色を具体的に思い描くほど、アンブシュアや息の配分が定まりやすくなります。プロの演奏を複数聴き、共通する要素と個性を切り分けて分析すると、模倣すべき基礎と自分の表現の余地が見えてきます。
旋律と伴奏の役割が入れ替わる編成では、前景と背景のバランス感覚が肝心です。音の芯を保ちながら、和声の中でどの帯域を支えるかを意識すると、合奏全体の透明度が高まります。
筋力トレーニングで腕を鍛える重要性
保持の安定は技術面だけでなく、基礎的な筋力と持久力にも支えられます。左前腕と握力、肩周囲の持久力、体幹の抗重力筋をバランスよく鍛えると、長時間の本番でもフォームが崩れにくくなります。
練習前後のストレッチや、肩甲骨の可動域を広げるエクササイズを取り入れると、疲労の偏りが減り、呼吸効率の改善にもつながります。過負荷を避け、段階的に回数や時間を調整すると安全に継続できます。
おすすめの音楽教室
「楽器は独学でもある程度は習得できますが、やはり限界があります。正しいフォームや効率的な練習方法をプロから学ぶことで、上達スピードが格段に違ってきます。独学で時間をかけて遠回りするよりも、最初からレッスンを受ける方が確実で挫折しにくいのです。
全国に教室を展開している シアーミュージック なら、初心者から経験者までレベルに合わせたマンツーマン指導が受けられます。さらに、いまなら無料体験レッスンも実施中。プロのサポートを受けながら、あなたも音楽をもっと楽しく、もっと早く上達させてみませんか?」
\無料体験レッスン実施中/
シアーミュージック公式サイトはコチラ
マーチングでユーフォニアムの持ち方まとめ
まとめ
- 左手で楽器を面で支え右手は操作に専念する
- ベルはやや斜めで視界を確保し投射を整える
- 顔を近づけず楽器を顔に合わせ姿勢を保つ
- 骨盤を立て胸郭を縦に拡げ呼吸路を確保する
- 歩幅と歩調を一定に体幹の上下動を抑える
- 楽器下部を腰に軽接触させ動作の揺れを制御する
- ウェストポーチは補助として使い過ぎに注意する
- フロントタイプは前方荷重を体幹で受け止める
- 口角の締め過ぎを避け口腔内の容積を保つ
- 息のスピードで音高を調整し喉は締めない
- ロングトーンとスラーで息の連続性を養う
- プロの演奏で理想の音色像を具体化する
- 役割に応じた前景と背景の音量設計を行う
- 左前腕肩周り体幹を段階的に鍛えて安定化
- 休憩とフォーム確認を習慣化し再現性を高める
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


