❕本ページはPRが含まれております
アルトサックス つば抜きについて、正しいお手入れや基本的なやり方、適切な頻度、そして水分が溜まりやすい部分の見極め方まで、迷いがちなたくさんの疑問を整理します。
演奏中や休憩中に気になるノイズ音への対処法、演奏後のクリーニングペーパーのシートの使い方、長く良い状態を保つための日常メンテナンスまで、要点を体系的に解説します。最短ルートで不快な雑音を減らし、楽器の寿命を伸ばしたい方に役立つ実践的な内容でお届けします。
この記事でわかること
- つば抜きの基本と正しい実施タイミング
- 本体とタンポそれぞれの手順と注意点
- ノイズ音やジージー音の原因と解決策
- 日常メンテナンスで劣化を防ぐコツ
アルトサックス つば抜きの基本知識
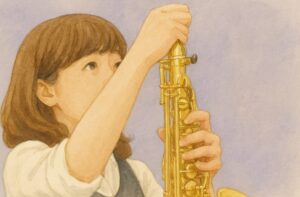
つば抜きをしないとどうなる
管内に水分が残ると、ズルズルやジージーといったノイズが発生しやすくなります。アルトサックスは管がJ字形で水分が留まりやすく、演奏の安定性にも影響します。さらに、残留水分は変色や錆の誘因となり、タンポが波打ったり接着が弱くなったりするおそれがあります。
重症化するとパーツ交換や研磨が必要になる場合があり、結果としてコストや演奏感の損失につながります。楽器本来の響きを長く保つためにも、演奏の区切りごとに水分を適切に除去することが肝要です。
正しいお手入れの手順について
お手入れは大きく二系統に分かれます。管内の水分を除去する工程と、タンポやキイ周りの水分と汚れを処理する工程です。
まずはネックとマウスピースを外し、スワブで本体内面を複数回通して水分を回収します。続いて、タンポにはクリーニングペーパーを軽く挟み、必要な油分を奪いすぎない力加減で押さえます。
仕上げに外装をクロスで拭き、水滴跡や指紋を取り除きます。これらを演奏後のルーティンとして定着させると、変色や錆の進行を抑え、次の演奏立ち上がりが安定しやすくなります。
本体の水分を抜く方法
ネックとマウスピースを外したら、ベル側から重り付きスワブの紐を通し、本体を返して管の細い方へ落とします。スワブは一回で終わらせず、4〜5回を目安に通して吸水させると効果的です。
途中で引っかかる感触がある場合は無理に引かず、軽く揺すってから抜きます。ネック単体にもスワブを通し、特にオクターブキーパイプ周りの水分を回収します。仕上げにトーンホール近辺を確認し、水滴が見える場合は再度スワブを通しておくと安心です。
タンポに適したつば抜き方法
タンポはフェルトや皮材が使われる繊細な部位です。濡れたまま放置すると膨張や接着不良の原因となります。クリーニングペーパーをタンポとトーンホールの間に挟み、キイを軽く押さえて水分を移します。
このとき力を入れすぎると必要な油分まで奪う可能性があるため、押し込みは最小限に留めます。水気が多いと感じるときだけ複数回行い、常用しすぎないことが要点です。水分を取り切った後は、しばらく開放して乾かす時間を確保すると安定します。
つば抜きの頻度と注意点
演奏後は必ず実施します。長時間の演奏や、寒い屋外から温かい室内へ移動した直後など結露が起きやすい状況では、休憩のたびに簡易的なつば抜きを追加すると安定します。
頻度を上げても本体への負担は基本的にありませんが、タンポのペーパー処理だけは過度にならないよう配慮が必要です。リハーサルと本番の間に短時間のつば抜きを挟むなど、場面に応じて強弱をつけることで、雑音の発生を大きく抑えられます。
サックスにおすすめの音楽教室
サックスをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のサックスレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のサックスレッスンを詳しく見る

アルトサックス つば抜きで防ぐトラブル

つばが溜まりやすい部分の解説
アルトサックスでは、構造上オクターブキー周りとリード周辺に水分が集まりやすくなります。ネックのオクターブキーパイプや、本体側の連結部付近は特に滞留しやすい箇所です。
リードでは樹脂製リードが吸水しにくいため、裏側に水分が残って鳴りのムラや雑音につながる場合があります。演奏前のチェックポイントを把握しておくと、ステージ上でのトラブルを最小化できます。
溜まりやすい部位の早見表
| 部位 | 溜まりやすさ | 主な要因 | 確認の目安 | 推奨ケア |
|---|---|---|---|---|
| ネックのオクターブキー | 高い | 管内結露と形状 | 息を強く通すと音が荒れる | ネック単体のスワブ通しとブローアウト |
| 本体連結部付近 | 中 | J字形による停滞 | キイ操作で微細な水音 | 本体スワブの複数回通し |
| リード裏面 | 中〜高 | 樹脂製は吸水しない | アタック時に雑音 | 取り外し拭き取りまたは軽いブロー |
ノイズ音が発生する原因とは
最も多いのはメンテナンス不足で、管内やタンポに残った水分が直接ノイズ源になります。次に多いのは演奏フォームの影響で、腹式呼吸が浅いと息に水分が多く混ざりやすく、結果として雑音が増えます。
マウスピースを強く噛む癖がある場合は下唇のコントロールが弱まり、リードに水分が流れ込みやすくなる傾向があります。
加えて、木製リードを交換しないまま長く使い続けると繊維が劣化し、発音のムラや雑音が増えます。以上の点を踏まえると、日常ケアと適切な奏法の両輪で対策することが要となります。
リード材質の比較(参考)
| 項目 | 木製リード | 樹脂リード |
|---|---|---|
| 吸水性 | あり 水分をある程度吸う | なし 裏面に水が残りやすい |
| 音色の傾向 | 豊かな倍音を得やすい | 安定しやすく天候に強い |
| ノイズの発生 | 劣化や水分過多で増える | 裏面の水滴で増える場合 |
| ケア | 乾燥と交換タイミング管理 | こまめな拭き取りが鍵 |
ジージーなるときの対処法
演奏後に本体のつば抜きをしてもジージーなる場合は、まずオクターブキー周りを疑います。ネックを外し、本体との結合部にタオルやハンカチを当ててオクターブキーを開き、演奏時と同様にしっかり息を吹き込みます。
これにより溜まった水分が排出されやすくなります。次に、リードを外して裏面を丁寧に拭き上げます。ステージ上など外せない状況では、マウスピースに軽く息を吹きかけて水分を飛ばす方法や、抵抗がなければ吸って除去する方法も即効性があります。
これらを順に試し、改善がない場合はタンポの状態やキイの密閉性を点検する段階に進みます。
日常のメンテナンスの重要性
日々のメンテナンスは、雑音の予防だけでなく、可動部の寿命や外観維持にも直結します。演奏後のスワブとタンポの軽いケアに加えて、外装をクロスで拭く習慣を持つと、水染みや指紋からの変色を抑えられます。
季節の変わり目や湿度の高い時期は結露が増えるため、休憩ごとの簡易つば抜きを取り入れると効果的です。リードは複数枚をローテーションし、木製なら状態に応じて早めに交換します。これらの積み重ねにより、急なトラブルに悩まされにくい安定したコンディションが実現します。
修理しても治らないときは【PR】
繊細なパーツを持つサックスは、度重なる修理で音質や吹奏感が変わってしまうことも少なくありません。修理しても治らないなら、無理に使い続けてストレスを抱えるよりも、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】に相談するのが賢い選択といえます。
【楽器の買取屋さん】なら高額査定が期待できるだけでなく、最速で最短30分の無料出張査定に対応しているため、忙しい方でも気軽に依頼可能です。
さらに、査定から買取までの流れがスピーディーなので、買い替え資金をすぐに確保できる点も魅力です。サックスを大切に扱ってきた想いを正当に評価してもらえる機会として、ぜひ活用してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ
サックス初心者の基礎練習ガイド
サックスがなかなか上達しない場合、基礎練習の考え方がズレていることが多いです。
「これで合っているのか不安」という初心者は、基礎練習のポイントをまとめた記事を確認してみてください。

アルトサックス つば抜きまとめと実践ポイント
まとめ
・演奏後は本体とネックのスワブ通しを複数回行う
・タンポはペーパーを軽く挟み水分のみを移す
・休憩中も状況に応じて簡易的なつば抜きを追加
・オクターブキー周りは結露しやすく重点的に確認
・樹脂リードは裏面に水が残りやすく拭き取りが必須
・ジージー音はネックのブローアウトで改善を狙う
・マウスピースを噛みすぎず下唇の働きを保つ
・腹式呼吸を整え息に余計な水分を含ませない
・木製リードは複数枚でローテーションして管理
・タンポケアはやりすぎず油分を奪わない力加減
・外装はクロスで拭き上げ変色と錆の誘因を減らす
・温度差の大きい移動後は結露対策を優先する
・引っかかりを感じたスワブは無理に引っ張らない
・ノイズが続く場合はキイの密閉と状態を点検
・改善が見られないときは専門店での診断を検討する



