❕本ページはPRが含まれております
トランペット ドイツ音名というテーマで検索していると、移調楽器ならではの音名の混乱や、合奏での伝達をどう整えるかが気になるはずです。
本記事では、ドイツ音名とは何か、イタリア音名との違い、移調楽器での実音の捉え方、そして演奏現場での使い分けまでを体系的に整理します。基礎から実践まで順番にたどることで、今日から迷わず音名でやり取りできる状態を目指します。
この記事でわかること
- ドイツ音名の基礎概念と読み方の全体像
- イタリア音名との役割分担と使い分けの要点
- 移調楽器での実音理解と合奏での伝達手順
- 練習に取り入れる具体的ステップと定着法
トランペットのドイツ音名を理解する

ドイツ音名を理解する
ドイツ音名とは何かをわかりやすく解説
ドイツ音名は、音の高さをアルファベットで示す体系で、C D E F G A H(Bはシではなくシのフラット)という並びで表します。
合奏現場では、実際に鳴っている音を基準に話を合わせるための共通語として機能します。例えば合奏中にCをくださいと伝えれば、各奏者が自分の楽器でコンサートCを出すための記譜音を選び、結果として同じ実音だけが会場に響きます。
この体系には派生音の表し方のルールがあります。基本はシャープにis、フラットにesを付けます。例として、FのシャープはFis、GのフラットはGesです。
BとHの扱いが特徴的で、Bがシのフラット、Hがシに相当します。この慣習を押さえるだけで、合奏でのやり取りが一段と明瞭になります。
イタリア音名とドイツ音名の違いを比較
イタリア音名(ドレミファソラシド)は、記譜上の音を読み上げるのに便利で、教育や練習で広く用いられます。
一方、ドイツ音名は実音基準のコミュニケーションに強みがあり、移調楽器が混在するアンサンブルでは意思疎通の軸になります。役割の違いを理解しておくと、場面に応じた使い分けが自然にできるようになります。
以下の表は、代表的な対応関係の早見表です。シについてはドイツ音名でH(ナチュラル)、B(フラット)になる点に注目してください。
| イタリア音名 | ドイツ音名(基本形) |
|---|---|
| ド | C |
| レ | D |
| ミ | E |
| ファ | F |
| ソ | G |
| ラ | A |
| シ | H |
派生音の基本ルールは次のとおりです。
| イタリア音名の例 | ドイツ音名の表記 |
|---|---|
| ファ♯ | Fis |
| ソ♯ | Gis |
| ミ♭ | Es |
| ラ♭ | As |
| シ♭ | B |
| シ | H |
移調楽器における音名の役割を知る
移調楽器は、記譜された音と実際に鳴る音が異なる性質を持ちます。トランペットB管なら記譜のドを吹くと実音はB(英語表記ではB♭)になり、F管のホルンでは記譜のドが実音Fとして響きます。
合奏でドをくださいとだけ伝えると、各楽器がそれぞれの記譜のドを出してしまい、実音が揃いません。そこで、Cをくださいのようにドイツ音名で実音を指定すれば、各奏者は自分の楽器に合わせて適切な記譜音を選び、同じ実音でそろえることができます。
この仕組みを知っておくと、合奏の初期合わせやチューニング、セクション内の確認が効率化します。結果として、音色やバランスの検討により多くの時間を割けるようになります。
ドイツ音名を覚えるメリットを整理する
ドイツ音名を使いこなせると、移調楽器間の連携が滑らかになります。具体的には、合奏中の指示が短く明確になり、チューニングや和音確認の時間が短縮されます。また、楽曲分析での和声や進行の把握が容易になるため、リハーサルの会話が統一され、演奏の仕上がりに直結します。
さらに、初見やキー変更の場面での対応力も上がります。実音基準での会話に慣れていると、転調が多い曲でも見通しを持って臨めます。以上の点を踏まえると、学ぶ労力に対して得られる効果が大きいと言えます。
音楽仲間とのやりとりで役立つ場面
セクションリーダーが和音の確認をするとき、C E Gを順に出してと短く伝えるだけで全員が実音でそろえられます。
ブラスアンサンブルでアーティキュレーションを合わせるときにも、いま鳴らしたEだけ軽くしてのように音名を実音で指定することで、誰がどの記譜音を担当していても意思疎通が成立します。
舞台上の限られた時間や騒音環境では、短い言葉で確実に伝わることが価値になります。ドイツ音名に統一することで、確認と再現のサイクルが速まり、音楽的な議論に集中しやすくなります。
トランペット ドイツ音名を使いこなす実践法

ドイツ音名を使いこなす実践法
トランペット演奏とドイツ音名の関係性
B管トランペットは、記譜の音より実音が全音低く響く楽器です。記譜のドを吹くと実音はB(英表記B♭)になります。
したがって、合奏でCを合わせる場合、トランペットは記譜のレを選べば、実音Cで全体と一致します。練習では、コンサートピッチとの対応を常に意識して音名を往復変換できるようにしておくと、現場での判断が速くなります。
具体的には、チューナーをコンサート表示に設定し、記譜の音と実音の両方を口で言いながら練習します。記譜のミを吹いて今は実音レだ、と即座に切り替えられるようになると、指示の理解も演奏の再現も安定します。
isやesを使ったシャープとフラットの表現
ドイツ音名では、シャープはis、フラットはesを付けて表します。Fis、Cis、Gis、Dis、Aisのように表記し、フラット系はDes、Es、Ges、As、Bという並びになります。読み方も合わせて口慣らししておくと、リハーサルで迷いません。
覚えやすいコツ
語尾の音感を体で覚えると定着が早まります。例えば、Fisはフィス、Gesはゲスと、短く歯切れよく発音します。視覚だけでなく発音練習を取り入れると、合奏中に瞬時に反応できるようになります。楽譜にカタカナで小さく読みを添えておくのも初期の助けになります。
BとHの特殊なルールを確認する
ドイツ音名では、Bがシのフラット、Hがシに相当します。この違いを取り違えると、和音確認で意図しない響きが生まれます。例えば、B-D-Fと指定された場合は、実音でシフラット・レ・ファの減三和音に相当します。一方、H-D-Fと指示されれば、シ・レ・ファで別の解釈になります。
半音上げや下げの扱いも合わせて整理しておくと安全です。HのシャープはHis、つまりシシャープで、Bのナチュラル相当はHになります。場面によっては、和声上の綴り分けが解釈の鍵になるため、表記の意味を理解しておくと、和音の方向性を共有しやすくなります。
移調楽器ごとの実音と記譜の違い
代表的な移調楽器について、記譜のドを演奏したときの実音を整理します。括弧内は、その楽器で記譜のドを吹いたときに鳴る実音です。
| 楽器例 | 実音(記譜のドを演奏) |
|---|---|
| フルート(C管) | C |
| トランペット(B管) | B(英表記B♭) |
| ホルン(F管) | F |
| コールアングレ(F管) | F |
| アルトホルン(Es管) | Es(英表記E♭) |
また、合奏でCをくださいと伝えた場合の各パートの記譜音の一例は次のとおりです。フルートはド、ホルンはソ、アルトホルンはラ、トランペットはレを選べば、全員が実音Cで一致します。こうした対応を体で覚えておくと、初合わせの精度が上がります。
初心者が練習に取り入れるステップ
まず、日課のロングトーンとスケールにドイツ音名の発声を組み合わせます。Cメジャーを吹く際に、C D E F G A H Cと声に出しながら進めることで、視覚と聴覚と運指の対応が結びつきます。
次に、移調対応の確認として、チューナーを見ながら記譜音と実音の両方を口に出し、頭の中での変換を習慣化します。
ミニドリルの例
一日三分でよいので、Cをくださいと言われたら自分の楽器で何を吹くかを即答する練習をします。トランペットならレ、F管ホルンならソ、Es管ならラという具合に、秒で答えられるようにしておきます。これを主要キーで反復すると、合奏での反応速度が確実に向上します。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
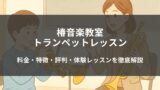
トランペットのドイツ音名まとめ
まとめ
・ドイツ音名は実音基準の共通語で合奏の連携を高める
・イタリア音名は記譜の読み上げに適し場面で使い分ける
・BはシのフラットでHがシという綴りの違いを定着させる
・シャープはisフラットはesという語尾の規則を体得する
・トランペットB管は記譜より実音が全音低い性質を持つ
・Cをくださいの指示で各奏者が実音Cに合わせて演奏する
・合奏のチューニングと和音確認が短時間で明瞭になる
・和声分析にドイツ音名を用いると議論が統一される
・口唱と運指と視覚を連動させて学習効率を高める
・チューナーをコンサート表示で使い実音感覚を養う
・主要キーで瞬時に記譜音へ変換する練習を継続する
・セクション内の指示を短く具体的に伝えられる
・初見や転調の多い曲でも見通しを持って対応できる
・役割の違いを理解し現場で最適な音名を選択する
・日々の基礎練に取り入れ実用レベルへ定着させる
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


