❕本ページはPRが含まれております
トランペット きれいな 音の出し方を探していると、息が続かない、音が荒れる、同じフレーズでも日によって響きが違うなど、具体的な悩みに直面しやすいものです。
本記事では、基礎から実践までを段階的に整理し、今日から取り組める練習手順とチェックポイントを明確に示します。
楽器経験の浅い方でも迷わず進められるよう、呼吸、姿勢、アンブシュア、基礎練習、教材選び、聴き込みと模倣、録音による振り返り、メンテナンスまでを一気通貫で解説します。
演奏の質を底上げしたい初学者から、もう一段階音色を洗練させたい初級者まで、確かな手応えにつながる方法を体系的に学べます。
この記事でわかること
- 音色を整えるための呼吸と姿勢の要点
- アンブシュアとロングトーンの具体的手順
- スケールや簡単曲、教材活用の進め方
- 録音とメンテナンスで改善を継続する方法
トランペット きれいな音の出し方の基本

きれいな音の出し方の基本
腹式呼吸と息の流れを整える
音色の源は息の質にあります。下腹部と背中側まで空気が満ちる感覚を意識し、胸だけで吸い込む浅い呼吸を避けます。
吸うときは肩を持ち上げず肋骨を外へ広げ、吐くときはお腹周りの支えを保ちながら気流を一定に流します。息のスピードが揺れると音色がざらつくため、安定したエアフローが鍵となります。
練習手順
1分間、鼻から静かに吸い口から細く長く吐く練習を繰り返します。メトロノームを60に設定し、吸う4拍・吐く8拍から始め、吐く拍数を12、16へと段階的に伸ばします。マウスピースを持たない状態で気流の均一さを体に刻み、次にマウスピース、最後に楽器を付けて同じ拍感で吹きます。
チェックポイント
頬や喉に余計な力が入っていないか、吐き切る終盤で音が痩せていないかを確認します。息の終わりで音量を無理に保とうとせず、支えをキープしたまま自然に閉じると響きが整います。
姿勢と体の使い方のチェック
姿勢は呼吸と直結します。足幅は肩幅、膝はロックせず軽く緩め、骨盤を立てて背骨を伸ばします。胸を張り過ぎると腹部が固まり息が浅くなります。楽器は持ち上げ過ぎず、ベルの角度が上下にぶれない位置で固定します。
立位と座位のポイント
立位では土踏まずに重心を置き、頭が前に出ないよう顎を引きます。座位では坐骨で座り、背もたれに頼りすぎない姿勢を保ちます。譜面台は目線と同じ高さに調整し、首や肩の緊張を避けます。
ありがちなクセの修正
肩で吸う、腰が反る、口角を過度に引き上げるなどは音色の細さや不安定さにつながります。毎回の練習冒頭に鏡で確認し、体の癖を早期に修正します。
アンブシュアを安定させる
アンブシュアは唇、口角、顎、歯列、舌位の協調です。マウスピースの位置は上下唇に無理のない比率で当て、口角は横に引きすぎず前へ支える意識を持ちます。圧力に頼ると高音は出ても音色が硬くなるため、気流の速さと口腔内の形で音程を支えます。
形成のコツ
発音はタ行の軽い舌先で、舌は歯茎の裏側付近に触れたらすぐ離します。上下の歯の隙間を保ち、顎を固めないことが響きを開く近道です。長時間の連続吹奏は疲労で微細なコントロールを失うため、短いセットで集中して行います。
ロングトーンで音質を鍛える
ロングトーンは音色の鏡です。各音を一定の息と音量で保ち、立ち上がり・中心・収束の3局面を丁寧に揃えます。極端なビブラートや揺れを避け、倍音のまとまりを耳で捉えます。
手順と配分
中音域の安定した音から始め、1音あたり8拍→12拍→16拍へ延ばします。日によって調子が異なるため、最初の5分は「今日の基準」を探る時間に当てると効率的です。
変化をつける練習
ppからmf、mfからffへと段階的にクレッシェンド・デクレッシェンドを行い、音色が痩せない限界を見極めます。終始、気流は止めずに支えを維持します。
メトロノームで均一化する
時間の均一性は音色の均一性に直結します。息のスピード、タンギング、指の動きがリズムに同期すると音の粒立ちが揃います。クリックに合わせて呼吸を始め、発音の直前で準備を終えておくと立ち上がりが整います。
| 目的 | 推奨テンポ | 実施方法 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 呼吸の均一化 | 60 | 吸う4拍、吐く8〜16拍 | 吐き終わりで音色を痩せさせない |
| タンギングの粒揃え | 72〜88 | タタタの等間隔発音 | 舌の離れを最短で戻す |
| 安定した立ち上がり | 60〜72 | 無音カウント→発音 | 先走らず拍頭で鳴らす |
トランペット きれいな音の出し方を実践

音の出し方を実践
スケールとアルペジオ練習
スケールとアルペジオは音域ごとの息の速度とアンブシュア調整を学ぶ最短ルートです。音程の階段を段差なくつなげる意識で、各音の入り口をそろえます。半音階は特に息の連続性を鍛え、音色のムラを洗い出します。
進め方
長音階をロングトーンの延長としてゆっくり始め、音ごとの質を確認します。次に三度スケール、アルペジオに広げ、テンポを段階的に上げます。テンポを上げても息の支えが細くならないよう、クリックに呼吸を合わせてから発音します。
仕上げの視点
上昇時と下降時で響きが変わらないか、音量のピークが中央に来ているかを毎回確かめると精度が上がります。
きらきら星など簡単曲で練習
旋律がシンプルな曲は、音色そのものに意識を集中できます。きらきら星、よろこびの歌、アメイジング・グレイスなどは範囲が狭く、フレーズの息配分を学びやすいレパートリーです。
活用のコツ
歌うように吹くことを最優先にし、音量を上げる前に音程と響きのまとまりを揃えます。フレーズの切れ目で息を回復し、終止音を押し込まず自然に収めると音色が品よく収束します。
| 曲名 | 音域の広さ | 学べるポイント | 難易度感 |
|---|---|---|---|
| きらきら星 | 狭い | 息の配分と音のつながり | 入門向け |
| よろこびの歌 | 中 | アーティキュレーション | 初級向け |
| アメイジング・グレイス | 中 | 音色のレガート表現 | 初級向け |
初級者はアーバン第1巻を活用
アーバン練習曲第1巻は基礎力の総合ドリルとして有用です。ロングトーン、リップスラー、スケール、エチュードが体系的に配置され、音色・音程・リズムを同時に鍛えられます。
取り組み方
毎回同じ順序で進めると慣れで流れ作業になりがちです。日替わりで開始セクションを入れ替え、集中力が高い時間帯に弱点課題を配置します。難所はテンポを落とし、音色が崩れない範囲でのみテンポアップします。
成果の測定
週ごとに録音して同じ課題を比較すると、倍音のまとまりや立ち上がりが可視化され、改善点が具体化します。
聴き込みと模倣で音色を学ぶ
美しい音色を出すには、まず美しい音を耳に染み込ませることが近道です。ウィントン・マルサリス、モーリス・アンドレ、セルゲイ・ナカリャコフといった名手の録音から、倍音の豊かさ、アタックの柔らかさ、フレージングの呼吸感を観察します。
模倣の手順
短いフレーズを選び、音価、アーティキュレーション、音量変化を真似します。ピッチやタイミングだけでなく、息の方向や舌の触れ方まで意識を広げると再現性が高まります。模倣は個性を消すのではなく、表現の語彙を増やす作業だと捉えると発見が多くなります。
録音とメンテで継続的に改善
録音は主観と客観のギャップを埋めます。スマートフォンでも十分効果があり、同じ課題を同条件で録って比較すると、日々の誤差が明確になります。
録音のポイント
マイクはベルから一定距離に固定し、部屋の残響を把握します。演奏直後ではなく数時間置いて聴き返すと、冷静に判断できます。
メンテナンスの基本
バルブオイルで動作を滑らかに保ち、スライドの清掃とグリスで気密を維持します。管内の水分や汚れは抵抗感を変え、音色のくすみにつながるため、定期的な洗浄が奏効します。小さな不具合を放置しないことが、響きの安定に直結します。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
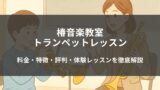
トランペット きれいな音の出し方まとめ
まとめ
・腹式呼吸で安定した気流を作り音色の土台を築く
・姿勢を整えて胸や肩の力みを減らし息の通りを確保する
・アンブシュアは口角で支え圧力依存を避け響きを保つ
・ロングトーンで立ち上がりと収束を揃え倍音を整える
・メトロノームに呼吸を合わせ時間軸の均一性を磨く
・スケールとアルペジオで音域ごとの息の速度を学ぶ
・半音階で連続性を鍛え音のつながりを滑らかにする
・簡単な旋律で音程と響きに集中し歌わせ方を学ぶ
・アーバン第1巻を軸に弱点を循環的に補強する
・名手の演奏を聴き込み模倣で表現の語彙を増やす
・定点録音で主観と客観の差を可視化して修正する
・バルブやスライドの整備で抵抗と発音を安定させる
・練習は短い集中セットで疲労由来の乱れを防ぐ
・上昇下降で響きが変わらないか毎回検証する
・日々の小さな改善の積み重ねが音色を洗練させる
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


