❕本ページはPRが含まれております
演奏後にトランペットのマウスピースが抜けない状況は、経験者にとっても焦りやすいトラブルです。
本記事では、原因の見極めから安全な外し方、やってはいけない行為、再発防止までを体系的に解説します。現場で試しやすい方法と専門店での対応の両面を整理し、保管やメンテナンスの注意点もまとめます。
トランペットのマウスピースが抜けないときに落ち着いて判断し、楽器を傷めずに解決へ進むための実践的なガイドです。
この記事でわかること
- 抜けない原因の主なパターンと見分け方
- 安全な外し方の手順と注意点
- やってはいけない行為と故障リスク
- 再発を防ぐ予防と日常メンテ
トランペットのマウスピースが抜けない原因と対処法

引用:Amazon
歪みが起こることで抜けなくなる理由
マウスピースのシャンクやマウスパイプの口元に小さな凹みや歪みが生じると、接触面の一部に引っかかりが生まれ、摩擦が不均一になります。落下や衝突、ケース内での圧迫でも目視しづらい変形は起こりやすく、特に学校備品のように使用者が多い楽器で見られます。
微細な凹凸が重なると、装着直後は問題なくても、温度変化や唇の圧力でさらに密着し、抜けにくさが増す傾向があります。小さな歪みでも累積すると固着の原因になり得るため、違和感が続く個体は早めに点検へ出す判断が賢明です。
余計な力を入れすぎてしまうケース
演奏前に強く押し込む癖があると、マウスピースが奥で楔のように固定されやすくなります。金属は演奏中の温度上昇でわずかに膨張するため、押し込み過多の状態では熱でさらに密着が強まります。
マウスピースとマウスパイプは基本的に潤滑油を使わない設計で、乾いた金属同士が面で当たるため、過度な力は固着の引き金になりがちです。装着は軽く差し込んで収まりが感じられた地点で止め、叩いたり回し込みすぎたりしない扱いが望ましいと考えられます。
埃や汚れが詰まることで起きるトラブル
繊維くずや埃、髪の毛、皮脂などの微細な汚れが入ると、接触面の平滑性が損なわれて抜けにくくなります。ケース内やクロスの毛羽が原因になることもあるため、装着前に口元を目視し、軽く拭き上げるだけでも予防につながります。
シャンク部分は硬いものでこすらず、柔らかいクロスで直線的に拭うのが基本です。日常の水洗いは管体内部の水分残りに注意し、完全乾燥後に収納する習慣が再発防止に役立ちます。
力任せに抜かないことの重要性
複数人で引っ張る、管体を固定して強くねじるといった方法は、ブレースやマウスパイプ、ベル根元の歪みを招くおそれがあります。メーカーの取扱説明では無理な力を加える外し方は避けるよう案内されているとされています。
瞬間的に外れても、見えないダメージが後の音程や吹奏感に影響することがあります。外れないときこそ一度手を止め、温度差を利用する方法や専用工具の使用、専門店での対応に切り替える判断が楽器保全の観点で得策です。
専用器具ヌッキーを使用する方法

引用:楽天
金管用のマウスピースプラー(通称ヌッキー)は、マウスピースのリムと受け側を均等に支え、ネジの力でまっすぐ引き抜く工具です。人の握力に頼らず、局所的な歪みを避けて外せるのが利点です。
使い方の手順
- 金属板の下側にシャンクを正しく載せ、上側の板がリムに均等に当たるよう調整します。
- 左右のネジを同じ回転量で少しずつ締め、軸が傾かないよう確認します。
- 抵抗が抜ける感触が出るまで、ゆっくり均等に締め続けます。
- 外れたら接触面を点検し、汚れを拭き取ってから収納します。
注意点
塗装やラッカー保護のため、接触部に薄い布を挟むと安心です。ネジを片側だけ先行させると斜め荷重になりやすいため、常に左右均等を意識します。異常な抵抗が続く場合は無理をせず専門店へ切り替えましょう。
トランペットのマウスピースが抜けないときの安全な解決策

引用:楽天
抜けないときの安全な解決策
冷やすことで金属を縮小させる方法
温度差を利用して金属の収縮を促す方法は、楽器への負荷が少ない対処として有効とされています。具体的にはマウスピース側を氷水で冷やし、管体のマウスパイプ付近は温かい蒸しタオルで保温し、寸法差を一時的に作ります。
手順の例:
- 氷水と蒸しタオルを準備します。
- 楽器を安定した場所に置き、マウスピースの先端が氷水に浸かる姿勢を確保します。
- マウスパイプ付近に蒸しタオルを巻き、1〜2分ほど温度差をつくります。
- 力を入れず水平にひねり、抵抗が減った感触を確かめながら外します。
注意点として、急激な加熱や冷凍庫での長時間冷却は結露や塗装ダメージの要因になり得るため避けます。水分が残らないよう作業後は丁寧に拭き上げます。
主な対処法の比較(状況判断の目安)
| 方法 | 準備物 | 手順難度 | 楽器へのリスク | 推奨度 |
|---|---|---|---|---|
| 専用器具(ヌッキー) | プラー本体 | 中 | 低(正しく使用時) | 高 |
| 冷やす温度差法 | 氷水・蒸しタオル | 低 | 低 | 中〜高 |
| ガムテープで握力補助 | 布・テープ | 低 | 中(塗装汚れ) | 中 |
| 軽い衝撃で緩める | 木槌・布 | 中 | 中〜高 | 低〜中 |
| 楽器店での取り外し | なし | 低 | 低 | 最高 |
ガムテープを使って滑りを防ぐ工夫
指先やマウスピース表面の皮脂で滑る場合、テープの粘着面でグリップを高めると、無用な力をかけずに引き方向の力を伝えやすくなります。テープはマウスピースから管体側へ橋渡しをするように貼り、折り返し部分を作ってつまめるようにすると保持が安定します。
作業時は斜めやこじりの方向に力をかけず、軸に沿ってまっすぐ引くことが肝要です。作業後は粘着残りを柔らかいクロスで除去し、溶剤の使用は仕上げ塗装を傷めるおそれがあるため避ける判断が無難です。
衝撃を与えて外す際の注意点
固着面の微小な噛み込みを解く目的で、布で保護したうえで木製ハンマーなどでごく軽くトントンと当てる方法があります。ポイントは一点集中で強打しないこと、マウスピース側と受け側の双方から均等に試すこと、そして打撃方向を軸線に対して直角にしないことです。
金槌など硬すぎる工具は仕上げを傷めやすく、打ち込みになって逆効果になる場合があります。わずかな衝撃で変化がなければ無理を続けず、他の方法へ切り替えます。
楽器店に修理を依頼するメリット
専門店では専用プラーや治具を用いた安全な取り外しに加え、歪みや凹みの確認、受け口の整形などの調整を同時に行ってもらえる場合があります。店舗によっては短時間での対応や、点検と簡易メンテナンスを含めたサービスが案内されることがあります。
料金は地域や店舗、作業内容で異なりますが、軽微な作業は比較的手頃に設定される例があるとされています。無理な自己流でダメージを広げるリスクを避けられる点が最大の利点です。
固着を防ぐための正しい予防方法
日常の扱いが再発防止の鍵となります。装着は軽く差し込むだけにとどめ、叩いて密着させる癖は改めます。異なるメーカーや規格のマウスピースはわずかな寸法差があり、固着や受け口の摩耗につながることがあるため、基本は適合品を用いる方が安全です。
保管時はケース内の緩衝材やクロスの毛羽が口元に付かないよう配慮し、装着前の目視チェックと軽い拭き上げを習慣化します。万一の落下や衝突後は、見た目に問題がなくても点検の機会を作ると安心です。
トランペットにおすすめの音楽教室
トランペットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のトランペットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のトランペットレッスンを詳しく見る
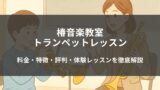
トランペットのマウスピースが抜けないときの注意点まとめ
まとめ
・歪みや凹みの蓄積が固着の根本原因になりやすい
・強い押し込みの癖は温度上昇で密着を助長する
・装着前の目視と拭き上げで汚れの挟み込みを防ぐ
・複数人で引っ張るなど力任せの方法は避ける
・専用プラーは軸を保ったまま安全に外せる
・ネジは左右均等に締めて斜め荷重を防止する
・温度差を利用する方法は低負荷で試しやすい
・テープでグリップ補助しこじらずに引く
・衝撃法は極めて軽く保護してから行う
・異常な抵抗が続く場合は直ちに中止する
・専門店なら取り外しと点検調整を同時に受けられる
・適合する規格のマウスピースを使用する
・叩き込みや回し込み過多の習慣を改める
・保管と持ち運びで口元の保護を徹底する
・トランペットのマウスピースが抜けない事態を予防する習慣を持つ
自宅に眠る楽器は楽器買取専門店がおすすめ
もし自宅に使っていない楽器があるなら、楽器買取専門店【楽器の買取屋さん】を活用するのがおすすめです。
出張買取や宅配買取に対応しているため、自分で楽器を運ぶ手間がなく、スムーズに査定から現金化まで進められます。買い替えや新しい楽器の購入資金に充てたい方は、まず無料査定を依頼してみてください。
\最短30分の無料出張査定/
楽器の買取屋さん公式サイトはコチラ


