❕本ページはPRが含まれております
クラリネットの高音域の練習で音がかすれる、音程が不安定になる、指が追いつかないといった悩みは少なくありません。原因の多くは息の扱いとアンブシュア、そして運指の整理不足にあります。
本記事では、ロングトーンとレジスターキーを軸に、息と口を一定に保ったまま音域をまたぐ方法を体系化し、毎日の練習に直結する手順としてまとめます。初学者から経験者まで活用できる再現性の高い手順で、無理なく高音の鳴りと音色を整えていきます。
この記事でわかること
- 息とアンブシュアを一定に保つ高音安定化の考え方
- レジスターキーを使ったロングトーンの手順
- 音程と音色の乱れを抑えるチェック方法
- 高音域に対応する運指の覚え方と定着法
クラリネット高音域練習 運指の基本ポイント

息のスピードを保つ練習法
高音を出そうとして息を強くしすぎると、口が締まり音が硬くなりやすくなります。狙うべきは、音域に関係なく息の流量とスピードを一定に保つことです。
下の音を吹いている最中から、すでに上の音が鳴るだけの息の流れを用意しておくと、音が切れずに自然に切り替わります。具体的には、低い音からレジスターキーで中音へ移る練習を用い、吹き始めから最後まで息の太さを変えない意識でロングトーンを行います。
息の速度を上げようとするよりも、吸い込んだ空気を余さず送り込む感覚を持つと、余計な力みが生じにくくなります。息の出口を喉の奥の広さで保ち、真っすぐ前へ送ることが鍵となります。
アンブシュアを安定させる方法
音が変わる瞬間に口を締めないことが非常に大切です。リードに対する歯と唇の圧力、下唇のクッション、口角の引き加減を一定に保ち、息だけで音高を跨ぎます。鏡で口元を確認し、音が変わるタイミングで顎や口角が動いていないかをチェックします。
下唇はリードに対して安定した支えになるよう軽く巻き、上の歯はマウスピースに安定して乗せます。口角は横に強く引きすぎず、上下方向の支えを感じられる位置に保ちます。結果として、音域が変わっても音色の統一感が生まれ、音程も落ち着いてきます。
ブレスコントロールの重要性
ブレスは音の準備そのものです。音を出し始める前の吸気で胸や肩に過剰な力が入ると、直後の息の流れが不安定になります。吸うときは静かに深く、吐くときは連続的で切れ目のない流れを保ちます。
吸気のポイント
・鼻と口を併用して静かに素早く吸い込みます
・下腹部だけでなく背中側の広がりも感じて容量を確保します
吐気のポイント
・音価全体で一定の流速を保ちます
・休符では形を崩さず、同じ吸い方で再開します
メトロノームで休符を管理し、吸って吐くリズムを毎回そろえると、再現性が高まります。
レジスターキーを使った基礎練習
レジスターキーを使ったロングトーンは、高音を安定させる近道です。狙いは、低い音と上の音を同じ息と口で吹くことにあります。音が変わる瞬間、親指が自然にキーを押すだけの感覚に近づけ、口や顎は一切動かさないようにします。
推奨手順(四分音符=60)
下表のサイクルを、低いミから始めてファ、ファシャープまで行い、中音のシ、ド、ドシャープへ対応させます。
| 手順 | 内容 | 拍数 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 1 | 低い音を伸ばす(例:ミ) | 8 | 息と口を一定に保つ確認 |
| 2 | 休み | 2 | 形を維持したまま吸気を整える |
| 3 | 低い音4拍+レジスターで上の音4拍(ミ→シ) | 8 | 息を変えずに音を切り替える |
| 4 | 休み | 2 | 同一の吸い方にリセット |
| 5 | 上の音を伸ばす(例:シ) | 8 | 上音での安定と音色の統一 |
| 6 | 次の音へ移行(例:ファ系へ) | 4 | 余裕を保って切り替える |
この流れを同じ指で3回伸ばす意識で進めると、口や息の癖が揃い、音色の統一が進みます。
運指を効率的に覚えるコツ
クラリネットは同じ指でオクターブ違いの音を出せないため、運指の整理が不可欠です。低いミと中音のシ、低いファと中音のド、低いファシャープと中音のドシャープは指の進み方が対応します。レジスター練習と五線紙への書き出しを併用すると、対応関係が視覚的に定着します。
練習中は必ず楽譜を見ながら行い、運指と音名を声に出して確認します。書く、見る、吹くの三段階で記憶経路を増やすことで、指の迷いが減り、テンポを上げても崩れにくくなります。
効果的に進めるクラリネット高音域練習

メトロノームを活用した練習方法
テンポ設定は再現性を生みます。四分音符=60から始め、音価と休符を常に同じ長さで管理します。呼吸のタイミングもメトロノームで統一し、1サイクルごとに吸う位置を固定します。テンポは内容が完全に安定してからごく小刻みに上げます。
練習サイクル例(四分音符=60)
| サイクル | 音の流れ | 吸気の位置 | ねらい |
|---|---|---|---|
| A | 低8 → 休2 → 低4+上4 → 休2 → 上8 | 休符開始時 | 息と口の形の固定 |
| B | Aを指だけ変えて反復 | 休符開始時 | 指の対応関係の定着 |
| C | Aの上音のみ音量を微調整 | 休符開始時 | 高音の鳴りの解像度向上 |
拍の出入り口が「同じ吸い方・同じ吐き方」で揃っているか、録音しながら確認すると精度が上がります。
音色のムラを減らすロングトーン
ロングトーンは音量ではなく密度を揃える意識で行います。音の立ち上がりから減衰まで、波打たない息を保ち、音が変わる瞬間も息の柱を絶やしません。アンブシュアは下唇のクッションと上歯の固定を保ち、顎を上下に揺らさないよう注意します。
音の曇りが出る場合は、息の流速が不足していることが多く、上音でうまく鳴らない原因になります。吸気量を増やし、音量ではなく息の連続性に意識を置くと、音色のムラが収まりやすくなります。
高音での音程を安定させる工夫
高音でピッチが高くなるのは、噛み込みや口角の引き過ぎが誘因になりがちです。上下の支えを保ちつつ、喉の奥を狭めないイメージを持つと、息の通り道が整います。指の動きは最短距離で迷いなく下ろし、キーの閉まりが遅れて息が抜けるのを防ぎます。
練習では、上音だけでチューナーを見続けるのではなく、低音から上音へ移る過程でのピッチの動きを耳で捉えます。遷移の中で高さが跳ね上がるなら、音が変わる瞬間に口が締まっている可能性が高いと考えられます。
低音から高音まで均一に吹く練習
目標は全ての音を同じ吹き方で鳴らすことです。低音で十分に鳴っているように感じても、上音で曇るなら息の流速が不足しています。低音の段階から上音に必要な息で吹くと、切り替え後の鳴りが明快になります。
練習は一息一音ではなく、一息で複数の音をまたぐ設計が効果的です。レジスター練習のサイクルを用い、休符を短く保ちつつ形を崩さないことが、均一化の近道になります。
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
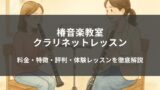
クラリネット高音域運指練習まとめ
まとめ
・低音から上音まで息の流速を一定に保つ
・音が変わる瞬間もアンブシュアを動かさない
・吸って吐くまでのリズムをメトロノームで固定する
・四分音符60の基準テンポで再現性を作る
・休符で形を崩さず同じ吸い方にリセットする
・レジスターキーは親指が自然に押す感覚で扱う
・低音8休2低4上4休2上8の型を反復する
・下唇のクッションと上歯の固定を安定させる
・高音の曇りは息不足と考え吸気量を見直す
・指は最短距離で迷いなく下ろし漏れを防ぐ
・運指の対応関係を五線紙に書き出して定着
・低音の段階から上音に必要な息で吹き始める
・録音して音色とピッチの遷移を客観視する
・テンポは安定確認後に小刻みに上げていく
・毎回同じ手順で練習し再現性で上達を早める


