❕本ページはPRが含まれております
クラリネット 奏者 呼び方について調べている方が、最短で正確な答えにたどり着けるよう情報を整理します。クラシックや吹奏楽、ジャズなど場面ごとに使われる名称の違いを比較し、意味の境界や使い分けのポイントを丁寧に解説します。
言葉としての成り立ちや、他楽器の呼称との関係も踏まえて、迷いなく使える知識に落とし込みます。
この記事でわかること
- 正式名称と通称の違いと使い分けを理解
- オーケストラと他ジャンルでの表現差を把握
- 他楽器の呼び方との対応関係を整理
- 名称が生まれた言語学的背景を学習
クラリネット奏者 呼び方の基本知識

クラリネッティストの意味と特徴
クラリネットを専門に演奏する奏者は、一般にクラリネッティストと呼ばれます。クラシックの文脈、とくにオーケストラや室内楽、教育現場の記述ではこの表記が広く通用します。
名称自体は、楽器名に語尾のistが付いて奏者を表す西洋語の慣例に沿ったもので、日本語でも自然な外来語として定着しています。
演奏分野は多岐にわたり、交響曲の中核を担うクラシックから、吹奏楽やジャズまで幅広く活躍しますが、名称としては分野を問わず用いて問題ありません。文章やプロフィールで統一的な表現にしたい場合は、クラリネッティストを基本形とすると整合性が取りやすくなります。
名称が生まれる仕組みの基礎
多くの楽器は、楽器名にistを付けると奏者名になります。例としてヴァイオリニスト、チェリスト、フルーティスト、オーボイスト、ファゴッティスト、トロンボニストなどが挙げられます。一方、トランペッターのようにerで表す例もありますが、数としてはist型が主流です。
クラリネッターとの違いを解説
クラリネッターという表現が使われる場面もあります。これは通称的で軽やかな響きがあり、口語やカジュアルな媒体で見かけることがあります。対してクラリネッティストは、公式プログラムや専門的な解説、プロフィールなどフォーマルな文脈で選ばれやすい名称です。
両者の意味はどちらもクラリネット奏者ですが、文脈に応じた語感の差が生じます。公演チラシや経歴紹介、教育機関の資料などではクラリネッティストを用いると品位と統一感が保てます。
SNSやポップな記事タイトルなど、親しみやすさを狙う場面ではクラリネット奏者あるいはクラリネッターも不自然ではありません。以上の点を踏まえると、正式表記が求められる局面ではクラリネッティストが適切だと考えられます。
ヴァイオリニストなど他楽器の呼び方
クラリネットの呼称を正しく理解するには、他楽器の呼び方との対応を押さえると見通しが良くなります。下の表は主要パートの代表的な名称です。ジャンルを横断して通用する基本形を示しています。
| 楽器 | 奏者の呼び方 | 備考 |
|---|---|---|
| ヴァイオリン | ヴァイオリニスト | ist型 |
| ヴィオラ | ヴィオリスト | ist型 |
| チェロ | チェリスト | ist型 |
| コントラバス | コントラバシニスト | オーケストラ文脈で使用 |
| フルート | フルーティスト | ist型 |
| クラリネット | クラリネッティスト(通称:クラリネッター) | 正式はクラリネッティスト |
| オーボエ | オーボイスト | ist型 |
| ファゴット | ファゴッティスト | 英語名はバスーン |
| ホルン | ホルニスト | ist型 |
| トランペット | トランペッター | er型 |
| トロンボーン | トロンボニスト | ist型 |
| チューバ | チュービスト | ist型 |
| ティンパニ | ティンパニスト | 打楽器の中心 |
| ピアノ | ピアニスト | 協奏曲や室内楽で活躍 |
| オルガン | オルガニスト | 教会音楽の系譜 |
| ハープ | ハーピスト | グリッサンドで象徴的 |
この対応を押さえると、未知の楽器でも呼称を推測しやすくなります。ist型が多数派で、er型は限られるという全体像が見えてきます。
オーボイストやフルーティストの名称
同じ木管でも、オーボイストやフルーティストはクラリネッティストと並ぶ基本語です。オーボエは温かみのある音色で旋律を担うことが多く、奏者名はオーボイストが定着しています。
フルートは明るく伸びやかな音色で、奏者はフルーティストと表します。いずれもクラリネットと同様にist型で、プログラムや教育資料の表記でも一貫性が保たれます。木管セクションを紹介する文章では、各楽器の役割とともに、これらの呼称を正確に記すと読み手の理解が深まります。

ファゴッティストとホルニストの呼称
低音を受け持つファゴットは、奏者をファゴッティストと呼びます。英語では楽器名をバスーンとも言いますが、オーケストラの日本語表記ではファゴットとファゴッティストの組み合わせがわかりやすい整理です。
金管のホルンの奏者はホルニストが基本形です。豊かなハーモニーを形作るセクションであるため、解説文では役割と合わせて名称を示すと、テキストの精度が高まります。
オーケストラ全体で見るクラリネット奏者呼び方

オーケストラ全体で見るクラリネット奏者呼び方
トランペッターやトロンボニストの事例
金管では、トランペットだけがトランペッターというer型で表されるのが特徴的です。同じ金管でもトロンボーンはトロンボニストとist型で表記します。この差異は語源上の慣行に基づくもので、意味としてはどちらも奏者を示します。
ジャズやポップスではプレイヤーという語も使われますが、オーケストラや教育現場の説明文では、トランペッターとトロンボニストを使い分けると整った記述になります。したがって、金管の中で唯一のer型としてトランペッターを覚えておくと混乱が減ります。
チェリストやヴィオリストの名称
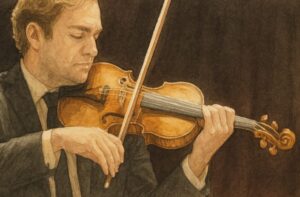
弦楽では、チェロの奏者はチェリスト、ヴィオラはヴィオリストが標準です。ヴァイオリンのヴァイオリニストと合わせ、弦セクションはist型が連続するため覚えやすい体系になっています。
曲目解説やプログラムの表記で、パート紹介にこれらの呼称を用いると、読み手は楽器構成を直感的に把握できます。以上の点を踏まえると、弦楽器の呼称は例外が少なく、表記揺れの心配が比較的少ないと言えます。
ティンパニストやピアニストの呼び名
打楽器の要であるティンパニは、奏者をティンパニストと表します。オーケストラでは複数のサイズを並べて音程を制御するため、専門性が高く、名称も定着しています。
鍵盤楽器ではピアノの奏者はピアニストが一般的です。オーケストラの中では協奏曲での登場が中心ですが、表記は分野を問わず一貫しています。両者ともに、プログラムや解説で名称を明示することで、役割の理解が一段と進みます。
オルガニストやハーピストの存在
オルガンの奏者はオルガニスト、ハープの奏者はハーピストが通例です。いずれもオーケストラでの出番は曲によって変動しますが、名称としては歴史的に安定しています。
特にハープは象徴的なグリッサンドで楽曲を彩るため、奏者名を正確に記すことが、編成の特色を伝えるうえで効果的です。オルガンは宗教音楽の伝統を背景に持ち、独奏や合唱作品での存在感も大きいため、オルガニストの表記はクラシック分野で広く通用しています。
クラリネットにおすすめの音楽教室
クラリネットをこれから始めたい方や、基礎からしっかり学びたい方には「椿音楽教室」のクラリネットレッスンがおすすめです。
椿音楽教室なら、経験豊富な講師が基礎から丁寧にサポートしてくれます。
無料体験レッスンもあるので、気軽に始められますよ♪
👉 椿音楽教室のクラリネットレッスンを詳しく見る
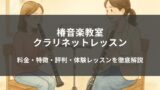
クラリネット奏者呼び方まとめ
まとめ
- クラリネット奏者の基本表記はクラリネッティスト
- 口語やカジュアル媒体ではクラリネッターも見られる
- 公式プロフィールや公演資料はクラリネッティストが適切
- 木管はフルーティストやオーボイストが標準表記
- 低音木管はファゴッティストの呼称が一般的
- 金管はトランペッターのみer型で例外的な存在
- トロンボーンはトロンボニストでist型に統一される
- 弦楽はヴァイオリニストやチェリストが基本形
- ヴィオラはヴィオリストで弦セクションの一貫性が高い
- 打楽器の中心はティンパニストという表記が定着
- 鍵盤楽器ではピアニストが分野を越えて通用する
- オルガニストとハーピストは歴史的に安定した名称
- ist型が多数派でer型はごく一部に限られる
- 文脈に応じて正式名と通称を使い分ける視点が重要
- 以上を踏まえクラリネット 奏者 呼び方の迷いを解消


