❕本ページはPRが含まれております
アルト サックス 移調表を探している方は、C譜からE♭譜へどう置き換えるか、B♭譜との違いは何か、度数や調号の考え方、そして実音と記譜音のズレをどう解釈すべきかで迷いやすいはずです。
本記事では、移調の原理を分解し、C譜を出発点にE♭譜へ変換する手順を具体的に示します。E♭譜に特有の調号の増減や、B♭譜との比較で起きる差、度数に基づく思考法、実音の確認方法まで一連の流れを整理し、演奏現場でそのまま活用できる形にまとめます。
移調に苦手意識がある方でも、鍵となるルールと例題で理解が進みます。
この記事でわかること
- C譜からE♭譜への移調原理と手順が分かる
- 調号と度数の関係を使った考え方を習得できる
- 実音と記譜音の違いを混乱なく整理できる
- B♭譜との比較で移調の全体像を把握できる
アルト サックス 移調表の基本理解

C譜とアルトサックスの違いを解説
アルトサックスはE♭管の移調楽器で、C譜をそのまま読むと実音が半音三つ高くなります。したがって、C譜をアルトで演奏するには、五線上の音を一段(線や間で一つ)下げるイメージで読み替え、調号も合わせて置き換えます。
実務上は、CメジャーをAメジャーに、GメジャーをEメジャーにするように、シャープを三つ増やす(またはフラットを三つ減らす)と覚えると素早く対応できます。こうすることで、譜面上の見た目と耳で聞こえる実音の差が整合し、アンサンブルでのピッチのズレを避けられます。
E♭譜で演奏するときの注意点
E♭譜に変換する際は、調号の置き換えと譜面上の位置の両方を同時に考えます。音符を三つ下げる処理に気を取られると、臨時記号の付け替えを忘れがちです。
シャープ系の調では三つ増えるため指使いが鋭くなり、運指の切り替えが増える傾向があります。逆にフラット系の調では三つ減るため、見た目がシンプルになる場合もあります。
F♯、B、Eのようにシャープとフラットが入れ替わる境目の調は、F♯をG♭、BをC♭、EをF♭と捉えるか、実務的には一音分下げるという発想で処理すると迷いにくくなります。
B♭譜との比較で理解を深める
B♭管(ソプラノやテナー)はC譜に対して音を一音上げる(半音二つ分上げる)考え方で、調号はシャープが二つ増えるかフラットが二つ減ります。五線上の移動量はアルトに比べて小さいため、読み替えは視覚的に把握しやすい側面があります。
シャープとフラットが入れ替わるのはF♯付近だけで、A♭と考えれば整合が取れます。B♭譜とE♭譜の違いを把握しておくと、スコア全体を見渡した際の整合や、移調譜の作成ミスを減らす助けになります。
実音と記譜音の関係を整理する
アルトサックスで記譜上のCを吹くと、実音はE♭として響きます。これは、楽器の設計上の基準音がE♭であるためで、同じ運指でも実音がピッチシフトして聞こえる構造に由来します。
アンサンブルでは、ピアノや弦楽器のC譜と合わせる場面が多いため、記譜音と実音のズレを頭の中で常に補正する習慣が役立ちます。
特に、ハーモニーを組み立てる際は、自分が書かれた音より三度下の実音を担当していることを意識すると、和声の役割が見通しやすくなります。
記譜音と実音の早見表(アルト)
| 記譜音 | 実音 |
|---|---|
| C | E♭ |
| D | F |
| E | G |
| F | A♭ |
| G | B♭ |
| A | C |
| B | D |
度数を使った移調の考え方
移調を度数で捉えると、処理が一貫します。アルトはC譜から見て短三度下げる発想で、書き換えは五線上で一段下げる操作に一致します。メロディの跳躍や経過音を度数で把握しておけば、臨時記号が増える場面でも流れを見失いません。
和音の場合は、各構成音をまとめて短三度下げるだけで整合が取れるため、ボイシングの再配置にも応用できます。結果として、譜面起こしや即興での転調対応力が向上します。
調号の増減ルールを覚える
E♭譜への変換では、シャープは三つ増やし、フラットは三つ減らすのが基礎です。例えば、CはA、FはD、E♭はCへ置き換えます。
F♯、B、Eのような境界の調は、理屈上はG♭、C♭、F♭と見なすと筋が通りますが、現場では読みやすさを優先し、一音分下げる感覚で混乱を避ける方法も有効です。
臨時記号が多い小節では、小節単位で先に調号を頭に入れ、次に音符位置の移動を行う順序にすると、書き換えの取りこぼしが減ります。
サークル・オブ・5thの使い方
サークル上で時計回りに進むとフラットが増え、反時計回りに進むとシャープが増えます。E♭譜への変換では、Cから三ステップ分の変化を加える意識を持つと、該当する調が素早く導けます。視覚化して覚えると、初見の曲でも即応しやすくなります。
アルト サックス 移調表を活用する実践法
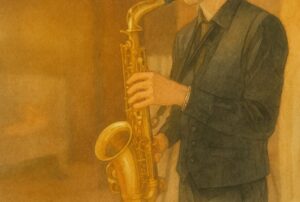
移調表を活用する実践法
移調の具体的な手順と練習方法
まず、原譜の調号を確認し、E♭譜ではシャープを三つ増やすかフラットを三つ減らすと決めます。次に、各音符を五線上で一段下に移し、臨時記号を新しい調に合わせて付け替えます。リズムやアーティキュレーションは原則としてそのまま保持します。
練習では、スケールとアルペジオを移調後の調で先に指へ馴染ませてから、楽曲の小節単位で読み替えに入ると効率的です。短いフレーズを繰り返し、正しい指使いと音程感を固定していく流れが定着に役立ちます。
調号を使った効率的な移調練習
調号中心の練習では、まずC、G、F、E♭など頻出の調を選び、E♭譜での対応調を即答できるまで繰り返します。視覚的に、調号が三つ変化することを先に処理し、次に五線位置の移動を行う順を徹底します。
F♯、B、Eの境界では、G♭、C♭、F♭として捉えるか、一音分下げるイメージで一貫性を保つと迷いが減ります。一定のテンポでメトロノームを使い、間違えた調だけを集中的に復習するスパイラル型の練習が効果を高めます。
実音を意識した移調の実用例
合奏でピアノのCメジャーに合わせる場合、アルトはAメジャーを読み、記譜のCが実音E♭になることを理解して音程を支えます。旋律のハイライトでは、元のメロディと自分の実音がどの度数で関係しているかを意識すると、和声の流れを損なわずに表情付けができます。
伴奏型のパターンでも、実音でのガイドトーン(3度と7度)を把握しておくと、和音進行に対して適切な重心を保てます。これらの意識付けにより、移調が単なる書き換えではなく、音楽的な再構成として機能します。
C譜からE♭譜へのスムーズな変換
下の表は、C譜の主な調をE♭サックスの記譜上の調へ置き換える早見表です。臨時記号の多い調では読みやすい表記(括弧内)を併記しています。
| Cの調 | E♭サックスの調(記譜) |
|---|---|
| C | A |
| G | E |
| D | B |
| A | F♯ |
| E | C♯ |
| B | G♯(A♭) |
| F♯ | D♯(E♭) |
| C♯ | A♯(B♭) |
| F | D |
| B♭ | G |
| E♭ | C |
| A♭ | F |
| D♭ | B♭ |
| G♭ | E♭ |
表を使う際は、まず原譜の調を特定し、対応するE♭サックスの調を選んだうえで、五線位置を一段下げます。複雑な転調が出てくる曲では、小節ごとに現在の調を素早く言語化し、表に照らして更新していくと安定します。
サックス初心者の基礎練習ガイド
サックスがなかなか上達しない場合、基礎練習の考え方がズレていることが多いです。
「これで合っているのか不安」という初心者は、基礎練習のポイントをまとめた記事を確認してみてください。

アルトサックス 移調表の活用法まとめ
まとめ
- アルトはC譜から三つの半音分下げて読み替える
- 調号はシャープ三つ増やすかフラット三つ減らす
- 記譜のCは実音でE♭に相当すると理解する
- 五線上で音符を一段下げる操作を基本にする
- F♯やBやEは入れ替わりに注意して処理する
- 度数で短三度下げる思考を軸に統一する
- 調号を先に処理し臨時記号を後で整える
- CやGやFなど頻出調から練習を始める
- スケールとアルペジオで指を準備しておく
- 実音のガイドトーンを意識して合奏する
- 表を用いて対応調を即座に選べるようにする
- 転調の都度現在の調を言語化して確認する
- B♭譜との違いを把握し全体整合を保つ
- サークルオブ5thで調の関係を視覚化する
- アルト サックス 移調表を常時参照し定着させる



